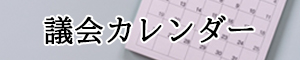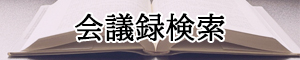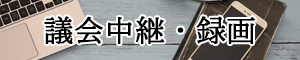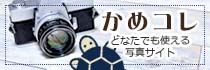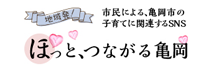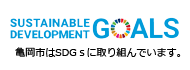本文
令和6年6月議会 本会議での討論
本会議で行われた討論を紹介します。
議員名をクリックすると、詳細な内容をご覧いただけます。
※公式な記録は、会議録<外部リンク>をご覧ください。
| 議案 | 賛成/反対 |
|---|---|
| 第3号議案 亀岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 反対 |
| 請願1 地方自治法改正に関する請願 | 賛成 |
| 議案 | 賛成/反対 |
|---|---|
| 第3号議案 亀岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 賛成 |
| 議案 | 賛成/反対 |
|---|---|
| 請願2 現行の健康保険証の存続を求める請願 | 賛成 |
| 意見書2 現行の健康保険証の存続を求める意見書(案) | 賛成 |
| 議案 | 賛成/反対 |
|---|---|
| 意見書1 改正された地方自治法において、国の地方自治体に対する補充的な指示の運用は拙速に進めないことを求める意見書(案) | 反対 |
| 議案 | 賛成/反対 |
|---|---|
| 意見書1 改正された地方自治法において、国の地方自治体に対する補充的な指示の運用は拙速に進めないことを求める意見書(案) | 賛成 |
| 議案 | 賛成/反対 |
|---|---|
| 意見書2 現行の健康保険証の存続を求める意見書(案) | 反対 |
討論の本文
|
私は、第3号議案 亀岡市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に反対の立場で討論を行います。 あらかじめ申し上げておきますが、この条例改正の主旨は、子ども医療費助成条例により実施する事務で規則に定めるものについて、市独自の施策ではあるが、国の個人番号を利用する特例として特定個人番号利用事務として、利用特定個人情報を利用することができるようにする条例の整備であり、長年の多くの市民が願っていたこども医療費の18歳までの無料化の事務が円滑に行えるようにするためのものであり、そのことができなくなるような事態を招きたいわけでは決してありません。条例の改正やその運用に問題があるというのではなく、認めるべきものではあるが、諸手を挙げて別段異論なく賛成するわけにはいかないという態度表明であります。たとえが正しくないかもしれませんが、市の職員が給与改定などの勤務条件改善の交渉の際、市当局案は不満であり反対を表明するが、やむなく議会へ給与条例改正案の上程は認めるといって妥結するのと同じような思いであります。 いわば入口のところで、国はマイナンバーカードをつくることも、つくったマイナンバーカードを保険証と紐づけするは任意だといい、選択の自由を国民に与えているにもかかわらず、出口という表現は正しくありませんが、保険証の利用のところでは、マイナ保険証一本化して、従来の保険証は廃止するという、いわば出口のところでは選択の自由がないわけです。総務省の今年2月の調査によると、マイナンバーカードを申請した人は8割弱です。しかし、申請したが受け取っていない人も相当数おられます。さらに、みなさん、マイナ保険証に紐づけられた人はどのくらいかご存じでしょうか。同調査では57%となっているのです。そしてマイナ保険証として利用した人の割合は1割程度です。そんな割合であるにもかかわらず、12月から保険証は使えませんというのは時期尚早だと、マイナンバーカードの普及推進に大賛成な方でさえおっしゃっています。マイナンバーカード申請や保険証との紐づけは任意であると、選択の自由を設けているのならば、保険証の利用でも、マイナ保険証か従来の保険証かの選択も自由にするべきです。これらが、私の感じている、委員長報告にもあった最大の矛盾点であります。 そのことをこの条例改正案で論ずるのは筋違いだというご意見に対しても、私は甘んじて受け入れるつもりですが、困っている市民の声も議会に届いている中、異論なく賛成することはできないということです。 この際、申し上げておきたいのは、18歳までの子やその保護者にも何らかの理由でマイナンバーカードを作っておられない方、マイナ保険証に紐づけされてない方が少なからずおられます。当然、万難を排して滞りなく、すべての対象者が亀岡市の制度を受けられるようにされると信じておりますが、担当部課にはそのことを強く求めまして、私の討論を終わります。 |
|
改正された地方自治法において、国の地方自治体に対する補充的な指示の運用は拙速に進めないことを求める意見書(案)に賛成の立場で討論を行います。 非常時に自治体に対する国の指示権を拡大する改正地方自治法は、先月19日の参院本会議で、賛成多数により可決、成立しました。 これまで国の指示権は、災害対策基本法や感染症法など個別の法律に定めがある場合にのみ認められていましたが、改正法により、個別法の規定がなくても、国が必要と判断し、閣議決定すれば指示権発動が可能となります。全国知事会の提言などを受けて、衆議院での採決時に法案修正がなされ、国の指示権行使が適切だったかを検証するため、国会への事後報告を義務付ける規定が入りました。ただ、国会による事前や事後の承認という、より厳格な手続きは盛り込まれていません。 指示権拡大を巡っては、首相の諮問機関である地方制度調査会が昨年末、法制化を答申しました。答申は、横浜港に停泊した大型客船での新型コロナ集団感染や各地の病床逼迫(ひっぱく)などで国と自治体間の調整が難航したのは、関係法が対応していなかったためだと結論付けていました。しかし、法案審議における追究で、コロナパンデミック時の大型客船、平たく言うと、ダイヤモンド・プリンセス号の対応でも、能登半島地震の職員派遣でも自治体が大変協力的に対応していることが、政府から報告され、非常時の国と自治体の調整・連携などが不十分だったという、「指示権」を必要とする法改正の理由・根拠は成り立っていません。国会審議では、指示権発動の要件が極めて曖昧な上、自治体との事前協議、調整の「義務」も「国会の関与」もないとの指摘や、乱用が懸念され、自治体への国の不当な介入を誘発し、拡大解釈される恐れがあるとの疑問を呈した。自治体を国の下に置き、地方自治を根本から破壊することにつながりかねないとの懸念の声があがりました。 果たして非常事態の際に、国は確かな指示を出せるのでしょうか。 状況が刻一刻と変わり、地域ごとに事情が異なる非常時に、国が的確な指示を出せるのか、地方自治体の不安は尽きません。東京新聞は「国がいつも正しいとは限らない」という表題で次のような論説を掲載されています。 指示権が発動できるのは、大規模災害や感染症のまん延といった「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」だが、この中には「その他」の事態も含まれる。解釈次第でどのような事態にも当てはまる抽象的な要件で、自治体にとっては「白紙委任」になりかねない。乱用の懸念に対する歯止めも用意されていない。指示権発動を巡り、政府を監視する役割がある国会に事前、事後の承認は必要だ。 2016年の熊本地震では、屋外の避難者を屋内に収容せよという国の「指示」を熊本県益城町役場ははねつけた。結果、後に起きた避難所の天井崩落に巻き込まれず、現場の機転が多くの命を救った。新型コロナ禍での全国一斉休校や「アベノマスク」の全戸配布は、非常時における国の判断の危うさを示す。この間、地方からは「国がいつも正しいとは限らない」との懸念が繰り返し表明されている。国民の命を守るためには何が最良の道なのか。国は自治体と十分に意思疎通する必要がある。安易に指示権を行使してはならない。 東京新聞に掲載された、これらの事例は、非常時における国の判断の危うさを示すものとして、広く国民に知られ指摘がされているところです。 全国知事会の提言や各自治体から出されている意見書と同様、今回の意見書は、そのような理由から、法律そのものを批判するのではなく、不十分な点をさらに明らかにして、その運用については慎重にすること、拙速に導入しないことを求めるものであり、議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたしまして、賛成討論とします。 |
|
私は、亀岡有志の会を代表して第3号議案について、賛成の立場で討論を行います。 亀岡市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する制定については、亀岡市こども医療費助成条例により実施される事務手続きで、この手続きをすることにより、マイナ保健証を持っておられる方の資格情報を本市の担当者から各保険組合に確認することができます。現状では、各個人から各健康保険組合へ資格確認書の申請手続きが必要となるところを省略されるものであります。 マイナ保険証を持っておられる方には申請手続きの大変な手間を必要とするものであり、速やかに条例の一部の改正が必要と考えます。 また、今後は国がマイナ保険証に変更するなかで、変更後の障害についての対策を考えていくことが重要と考えます。 以上を私の賛成討論とします。 |
|
私は、日本共産党亀岡市議会議員団を代表して、「現行の健康保険証の存続を求める請願」について、賛成の立場で討論を行います。 「国民皆保険」の制度のもと、誰もが安心して保険による診療が受けられるために、現行の健康保険証の存続を求めるものです。 環境市民厚生常任委員会6月25日では、1941筆の署名と共に「現行の健康保険証の存続を求める請願」を受けました。陳述を受けたあとの審議で、 ・障がいのある方や高齢者にとって、健康保険証がなくなることへの不安を陳述者が述べている点は理解できる。 ・障がいのある方のマイナンバーカード申請ができない状況があり、そのことへの対応が課題であることも共有できる。 との意見が出されました。 この請願は、亀岡市民の中で現行の保険証を存続してほしいという切なる市民の声です。国の制度そのものに意見するものではありません。議会として、困っている市民の声をしっかりと聞く姿勢が求められています。 しかし、採決の結果は、今年12月で保険証を発行しなくなってもその保険証が使える1年の猶予がある。現時点では時期尚早である。今後国はしっかりと対策をとるはずである。健康保険証を残すことは、国のデジタル化の妨げとなる。との意見が出され、「不採択」となりました。 全国では、「保険証存続の意見書」を国に提出している自治体があります。京都府内では長岡京市や向日市、精華町が意見書の提出をしました。全国でも、私が確認した中では152(2024年6月6日更新版)自治体が意見書を提出しています。 「誰一人とりのこさない亀岡市」ですから、ぜひ市民の声を重く受け止めて、健康保険証の存続を求める請願が採択されることを望んで、賛成討論といたします。 |
|
私は、日本共産党亀岡市議会議員団を代表して、「現行の健康保険証の存続を求める意見書(案)」について、賛成の立場で討論を行います。 この意見書(案)は、亀岡市民の中で現行の保険証を存続してほしいという切なる市民の声です。国が進めるマイナンバーカードやマイナンバーと保険証の一体化に意見するものではありません。マイナンバーカードを作ることも、保険証と紐づけることも任意であるという、選択の自由があります。保険証についてもカードか紙かの選択の自由が与えられて当然のはずです。しかし、従来の保険証が廃止されるという、選択の自由がなくなることに対して困っている市民が、少なからずいるので国が配慮してほしいというものなのです。 議会として、今、困っている市民の声に対してどう応えるか!それが問われています。 「誰一人とりのこさない亀岡市」ですから特に障がいのある方や高齢者の方、少数であっても不安の声に答えることが大切です。議員の皆様の賛同を得て、健康保険証の存続を求める意見書(案)が採択されることを望んで、賛成討論といたします。 |
|
私は、「改正された地方自治法において、国の地方自治体に対する補充的な指示の運用は拙速に進めないことを求める」意見書案について、反対の立場から討論いたします。 まず最初に、本改正案の大きな柱は「DXの進展を踏まえた対応」、「地域の多様な主体の連携及び協働の推進」、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例」の3点でございますが、包括的に討論をさせていただきます。 皆さま思い出していただきたい。全国、どこの自治体もコロナ禍において、自治体間で対応や対策の差が生じておりました。現行法に定めのない状況において、既存の法律に権限が明示されず、法の不存在の中、国も地方自治体も手探りで動かなければならないことも多々あったのは、亀岡市議会の中でも、感じていた皆さまも多かったと思います。 分かりやすく言うと、本改正で国と地方自治体の役割は明確にされ、有事対応が今よりも機動的に実施対応しやすくとなると認識をしております。 同時に個別法で対応が困難な事態における国の責任を明確にする観点からも本改正案の意義があると考えます。 というのも、「個別法で想定されていない事態において国には果たすべき役割があって、これを責任を持って果たす必要がある」と政府見解を先の国会でも総務大臣が述べており、有事法制の必要性、また責任明確化の必要性が明らかになっております。 ご承知のとおり、各自治体はコロナ禍で対応計画を立案し、準備、実行に努めてきたのが事実。 非常事態において対策を現場で行うのは自治体であり、そのための権限や財源、人的資源等が必要であった事は周知の事実です。決して、個別法の役割と重要性を決して否定するものではありませんので、誤解ないよう、あえてお伝えをさせていただきます。 本法改正は、現時点で、想定し難い国民の生命等を守るために必要な措置であって、かつ個別法に規定がない場合に限り、限定的な要件、適正な手続の下、自治体と情報共有、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものと述べているとおり、平時に用いるものではないと事実、明言しております。 切り取った考えをされていないと思いますが、ワンセットに根拠に基づき考えていくべきだろうと思います。 今後、ますます地方の首長の役割は、日本国全体にとってもかつてなく重要なものになると考えており、 本改正案によって不測の事態に対する権限が整理され、危機対応に役立つことは明らかであり、国と地方がより連携を取りやすく、役割が明確に分担されるものである事をお伝えし、多様化する危機対応のために必要な制度だと考え、本意見書の反対討論とさせていただきます。 |
|
私は、日本共産党亀岡市議会議員団を代表して、「改正された地方自治法において、国の地方自治体に対する補充的な指示の運用は拙速に進めないことを求める意見書(案)」について、賛成の立場で討論を行います。 今回の法改正により、個別法に規定がなくても国が必要と判断し、閣議決定すれば指示権発動が可能になりました。これまで国と地方は「対等・協力」の関係で、国の関与は必要最小限となっていましたが、今回の改正はその流れに逆行するものとして、日弁連・全国知事会、そして多くの自治体から懸念の声が上がっていました。お隣の南丹市では「非平時にかかる地方自治法の改正にあたっては地方自治の本旨が守られることを求める意見書」が全会一致で採択され、令和6年3月28日付けで衆参議長と内閣総理大臣あてに意見書が提出されています。 国会審議の中で指示権の行使は「必要最小限」とし、事前に自治体と協議することも付帯決議に盛り込まれましたが、指示の範囲が未だ曖昧であり、指示を拒否できないことなど国の運用を懸念する声も根強くあります。地方自治の本旨に反し、地方分権に逆行することのないよう「国の補充的な指示の運用は拙速に進めないことを求める意見書(案)」が採択されることを望んで、賛成討論といたします。 |
| 私は、会派経政会を代表して現行の健康保険証の存続を求める意見書(案)に反対の立場で討論します。
現在マイナンバーカードと健康保険をリンクした、いわゆるマイナ保険証を国として進めているところであります。 今後マイナ保険証の利用により、通院など医療機関での受付が自動化される事や、正確なデータに基づく診療や薬の処方を受けることが可能となり、利便性が向上することはすでにご案内の通りであります。 一方こうした国の動向にそった形で本市での各医療機関においては、マイナ保険証に対応するべく、システムの導入や改修が行なわれているところであります。 本市におけるマイナ保険証に対応出来る医療機関の現状についてでありますが、本年3月24日時点の国の発表によると、91件ある医療機関のうち既に86件がマイナ保険証への対応が可能となっており、薬局においては29件中28件が対応可能である事が明らかになっているところであります。 例えば、本市において対応が遅れており、こうした体制整備が不十分であるとするならば、当該意見書の趣旨は理解できるものの、紹介の通り、ほぼ体制が整っている中において何故、当該意見書を提案されるのか甚だ疑問であると言わざるをえません。 また、移行期間は別として先々まで現行の健康保険証をマイナ保険証と並行して存続させることは、かえって業務を煩雑化させる事となり、現場を混乱させる恐れがあると推察します。 あくまで本年12月2日をもって現行保険証の「新規発行」が停止されるのであって、すぐさま紙の保険証が使用できなくなる訳ではありません。 一部では医療機関での診療が受けられなくなり、受診の空白期間が生まれるかのような印象を与えかねない説明を聞くこともありますが、こうしたことは悪戯にただ市民の不安をあおっておられるとしか考えられないところである。 重ねて申し上げるとするならば、現行保険証は令和7年秋ごろまで利用できること、さらにはマイナンバーカードと保険証をリンクされてない場合や、そもそもマイナンバーカードをお持ちでない方には、無料で「資格確認書」が発行され、当然切れ目なく診療を受けることが出来る事を申し添えたいと思う。 なお、こうした正しい情報を市民のお一人お一人に丁寧に周知すべきは行政としての責務であること、国ならび政府には新たな制度であるマイナ保険証への移行により、誰ひとり不利益を受けることが無いように、常に検証を行い精度を上げることを望み現行の健康保険証の存続を求める意見書(案)についての反対討論といたします。 |