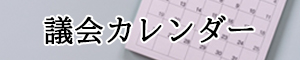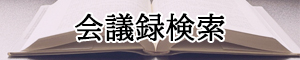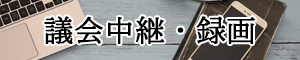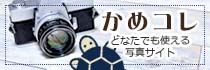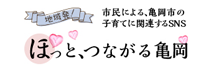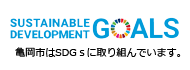本文
令和4年9月議会 本会議での討論
本会議で行われた討論を紹介します。
議員名をクリックすると、詳細な内容をご覧いただけます。
| 議案 | 賛成/反対 |
|---|---|
| 第9号議案 亀岡市立小学校設置条例等の一部改正 | 反対 |
| 第12号議案 令和3年度亀岡市一般会計決算 | 反対 |
| 議案 | 賛成/反対 |
|---|---|
| 第1号議案 令和4年度亀岡市一般会計補正予算(第3号) | 賛成 |
| 第12号議案 令和3年度亀岡市一般会計決算 | 賛成 |
| 議案 | 賛成/反対 |
|---|---|
| 第12号議案 令和3年度亀岡市一般会計決算 | 賛成 |
| 議案 | 賛成/反対 |
|---|---|
| 第12号議案 令和3年度亀岡市一般会計決算 | 賛成 |
討論の本文
|
私は、共産党議員団を代表して、第9号議案、亀岡市立小学校設置条例等の一部を改正する条例の制定について、および、第12号議案、令和3年度亀岡市一般会計決算認定について、それぞれ反対の立場で討論を行います。 まず、第9号議案は、本梅小学校、畑野小学校、青野小学校、育親中学校を閉校し、新たに育親学園を義務教育学校として設置するための条例改定です。 議案審査の中で、私は、3つの小学校より規模の小さい、東別院小学校、西別院小学校、吉川小学校、および同規模の保津小学校が、特認校制度の活用も含め、単独で存続しているのに、この3小学校を統合する根拠は何かと質問しましたが、担当課からは明確な答弁が返ってこず、学校規模適正化基本方針に則って行うということだけでした。昨年、9月の別院中学校編入に係る条例案の反対討論でも長澤満議員が申したとおり、そもそも、学校規模適正化は、国において、財務省が全国の小・中学校を標準規模にすれば、教育予算を削減できるとの試算を示し、その強い意向を受けて、文部科学省が打ち出してきたものです。各地のさまざまな教育の実践の中から、その向上のための課題を探求して出てきたものではありません。私や教育長が現場で教育実践を積み重ねていたころには聞いたこともない論理です。亀岡市教育委員会は、これまでから特色ある学校づくり、ふるさとを愛する教育を重視されてきました。また、本市の目指すSDGsを貫く理念は、さまざまな分野で多様性を大切にすることです。これらから見ても、規模の画一化を図る学校規模適正化は疑問だらけです。 学校規模適正化基本方針については、当初出されたものは、短期的な取組として、「すでに問題が生じており、教育環境が損なわれている学校」に対して行うと大変失礼な記述となっていましたので、私は、児童生徒、保護者、地域、教職員にとって、自分たちの学校が「問題がある学校」と定義されることは許せないと申し上げたところ、「すでに課題が生じており」という文言に訂正されましたが、「教育環境が損なわれている学校」という記述は変わっていません。これまでの教育部の説明では「複式学級の解消などよりよい教育環境を目指して」という言葉が使われてきました。複式学級はどんなに人数が少ない学年でも担任を一人配置するよう国や府が基準を改めればよいだけのことですが、なかなかそうはいきません。しかし、複式学級は特別の努力を要しますが、決して悪い環境ではありません。 普通は特別な手立てをとらないとできない異学年交流が毎日できるわけです。授業はガイド学習という手法を取ります。担任の先生がもう一方の学年の指導を行う際、児童が進め役を決めて進行し、全員が授業内容を予習してきて授業に臨み、分からないところだけを担任の先生が指導するわけです。ですから、受け身でなく、より主体的に授業を進める立場で子どもたちが活躍します。これからの教育で重視される「アクティヴラーンニング」の精神を先取りした学習方法が、複式学級の授業づくりの中で貴重な財産として受け継がれているのです。 勤務していた、複式学級を含む小規模校で、私が担任した学年は複式学級ではありませんでしたが、このガイド学習を取り入れた学習を毎日行ってきました。町内3小学校とも連携して同じ学年の学級にも呼びかけて学習を行いました。中学校で一緒になったその学年は、その後も意欲的に学習に取組、京都府内でトップクラスの学力テストの結果を出し、先生方も喜んでおられました。次の年に4つの小学校が一つになり、1学級が40人近くいっぱいになりました。その学年が中学校で学習の成果がどうであったかは言わずもがなです。おまけに、ほとんどがバス通学になり、6年生の5月に実施予定だった修学旅行も、季節外れのインフルエンザの流行で中止となりました。 世界では先進国が教育にしっかりとお金をかけて、1学級の人数を減らし、学校規模も100人程度を目安にして、十分な教職員数を配置して学習指導に取り組んでいます。これが世界のスタンダードなのです。 これらのように主体的な学びの実現という点でも、新たな感染症による困難を経験したのちの感染リスクを軽減する手だてという点でも、世界のスタンダードの教育に追いつくという点でも、日本の教育施策は逆行しているのです。これは国の教育施策の責任ではありますが、亀岡市においては、そんな学校規模適正化に与せず、多様性とふるさとの良さを尊重する学校教育を、なんとか踏ん張って維持していただきたいのです。 教育論として申し上げたこと、この亀岡市でも児童生徒の皆さんは実感されています。社会性も、主体性も、仲間どうしの切磋琢磨も、小規模校で十分に培われるし、逆に小規模校の教育にこそ希望とヒントがあります。 7 年前の子ども議会で質問した本梅小学校の児童の発言はそれを表しています。 『僕は、3年前に亀岡で一番の大規模校から小規模校に転校しました。転校したとき、「すごく小さいな」「友達できるかな」など、不安でいっぱいでした。しかし、その不安はすぐになくなりました。同じ学年の友達だけではなく、全校のみんなが僕に優しく声をかけてくれ、すぐにみんなと友達になれました。僕は、心の底からみんなに感謝しました。小規模校だからこそだと思いました。また、大規模校にいたときは、何をするにも自分から積極的に発言しようと思いませんでした。人数が多く、誰かが発言してくれたからです。何をするにも人に頼っていました。しかし、この学校に来て驚きました。全員が自分の意見を積極的に答えているからです。少人数なので、発言する機会が増えます。一人一人の自主性が必要であり、一人一人がリーダーになれるのです。最初は本当に恥ずかしかったけど、みんなに負けないよう、一生懸命発言することで、僕は何事にも積極的な人間になれたと思います。最近は、近くの学校で統廃合が行われていますが、小規模校は大規模校にはないよいところがたくさんあります。こうした僕たちの思いも積極的に聞いてほしいと思います。』 また、これを聞いた保津小学校の児童が『僕の通っている保津小学校も、全校児童47名の小さな学校です。6年生は毎年、保津町の歴史や保津の火祭りの歴史を地域の方から教えてもらっています。僕の生まれた町のことをいろいろ教えてもらうことで、保津町をこれからも大切にしていこうという気持ちになりました。これは、保津町に保津小学校があるからできたかもしれません。町に小学校があり続けるということは、町が元気にあり続けることだと思いました。』と発言されました。これらは児童の皆さんにも、聞いていた議員はじめ大人の皆さんにも大きな感動を与えるものでした。 このように発言された皆さんは、そして中学生議会で別院中学校の存続を訴えられた生徒さんも、ちょうど選挙権を得た年齢になっておられますが、この間の、別院中学校、本梅小学校など3小学校の統合をどんな気持ちで知ることになるのでしょうか。 また、全国各地で、鳴り物入りで始まった小中一貫義務教育学校も、当初期待されていた教育効果がさほど上がらず、さまざまな課題が浮かび上がり、拠点校として注目される中での教職員の多忙化に拍車がかかり、疲弊の度合いが高まっていると聞きます。中1ギャップの解消と言われましたが、小学校でどのような生徒指導や進路指導教育をするかで中1ギャップは容易に克服できるのです。クラス替えがなくても人間関係の固定化を招かないこともできます。逆に、いろいろな小学校から集まってきた中学校では、人間関係の再編成がなされ、自己肯定感や他人の長所の再認識が高まり、生徒が成長するチャンスとなります。多くの義務教育学校では、9年間メンバーが変わらないことによる中だるみ現象が起きるという課題が浮かび上がっています。 現場の先生方もいろいろな意見をお持ちだと思います。でも、そうなったらやらざるを得ないのです。大規模であれ小規模であれ、統廃合されようとも、子どもたちにいやな思いをさせないようにがんばられるのです。校長先生を通じては浮かび上がってこない苦労や悩みがそこにはあります。 いずれにせよ、文科省発案でない財務省に押し付けられた学校規模適正化による、小規模校の閉校は、子どもファーストではなく、大人の都合による考え方であり、教育に携わってきた私としては断じて容認できません。 以上のような点を指摘し、第9号議案に対する反対討論といたします。
次に、第12号議案、令和3年度亀岡市一般会計決算認定についてであります。 令和3年度当初予算について、共産党議員団は、市民にとって必要な施策・事業の経費が多数計上されていることを認識しつつも、市民福祉の増進に必要な予算計上であるかをしっかりと吟味する中で、不要不急な事業、施策、本来の事業の趣旨から逸脱していると言わざるを得ないもの、これまでの実績や使途が不透明であると言わざるを得ないものが幾つも含まれており、再検討を求めるべきとして、反対いたしました。 3款民生費、1項社会福祉費、8目人権啓発費のうち、人権啓発推進経費の人権擁護施策推進・要求亀岡実行委員会助成金について問題性、同じく10目文化センター運営費地域交流促進経費のうち、隣保館デイサービス事業をはじめとする幾つかの事業についての不明瞭あるいは不適切な支出、業務委託の適格性、また、4款衛生費、1項保健衛生費、4目環境衛生費、火葬場等経費に係る立地場所や住民合意に係る問題点、9款消防費、1項消防費、1目常備消防費の京都中部広域消防組合負担金については、京都中・北部地域消防指令センター共同運用に係る問題点などを指摘しましたが、そのまま計画の推進、予算の執行が行われました。 また、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、くらしの資金貸付経費の充実や、同じく5目老人福祉費、高齢者生活支援経費の緊急通報装置設置事業委託料における、対象の拡大や無料化を訴えましたが。これらの福祉分野の施策は後退したままです。 中でも今回一つ取り上げて強く指摘したいのは、10款教育費、5項社会教育費、1目社会教育総務費のうちのガレリアかめおか運営経費です。長寿命化計画に基づいて、このガレリアかめおかは令和41年までかけて保たせるために120億円の支出を見込んでいます。今年度当初予算審査の際、桂川市長自身が「そんなにかかるの」と思わず言葉にされていました。 令和41年というと今から37年後であります。そこまであの建物を保たせられたかどうか見届けることができるのは、この議場で一体何人おられるのでしょうか。そのことは別として、既存の建物を大事に使い活用することは大事なことかもしれません。しかし、一方で、環境先進都市、SDGs未来都市亀岡市として、あの建物が37年後まで残っていることはどうなのかなと思います。空調が効きにくく、冷暖房にも多大なエネルギーが必要となり、決してエコな建造物とは言えないものです。現に、毎年2億円を投入しないと運営できない状況が続いています。使い勝手が悪く、どの部屋でも音楽演奏ができない、私も響ホールで映画を時々観ますが音がワンワンとなって本当に響きホールです。 私は、除却しながら、横の緑地に新しいものを建てることも検討してはどうかと思いますが、そのような考えはないとのことでした。せめて、除却するにはどの程度の費用を要するか、さらに新しいものをつくるとしたらどのような費用となるのか、それぐらいは、検討されても良いのではないかと思います。ひょっとしたら、120億円の範囲内で除却と新築ができるかもしれません。何も巨大な施設ハコものをつくる必要はありません。太陽光発電と蓄電池をはじめ、エコで効率よい文化ホール、感染症にも強い空調や安全対策、誰にとっても使いやすいユニバーサルデザイン、これらの実現のために環境先進を目指す企業の協力を募る、除却した土地は、有効に利用し、キッチンカーや地元の農家、商店街マルシェのできる場所も取り入れた道の駅、周辺からのふるさとバスの乗り継ぎポイントなど、夢のある活用をしたいものです。一極集中でなく、市民の文化活動などは人口の多い、東部地域と、人口が増えつつある、大井・千代川地域など各地に分散して、効率良い建物を検討するなど、そのような考え方は全く非現実的でしょうか。 昨年の修善工事の契約案件に共産党議員団は反対しました。請負事業者とそこからの下請け事業者への疑問などが地元事業者からたくさん出されたからです。 私は、昨年度、工事期間中、週に1度のペースで、実際にガレリアかめおかに足を運び、工事の様子を見守ってきましたが、工事関係車両駐車場には、大阪、なにわ、神戸ナンバーの車が、いつでもたくさん並んでいました。 あんな特殊なガラスのコーティングなど地元事業者ではできないからです。 これから37年間あのガレリアかめおかを保たせるためには、同じようなことが次々と起こるのではないですか。地元事業者が活躍しにくい、使い勝手の悪い、建物を120億円以上、37年もかけて保たせることは本当に亀岡のためになるのでしょうか。 37年後、環境先進都市として、またSDGs未来都市として、亀岡市が憧れのまちとして発展していることを望んでいます。その時、あの建物がかろうじて維持されているというのはなんともミスマッチに思えます。 今一度考え直していただくことを求めて、反対討論とします。 |
| 討論の本文 |
|---|
|
私は、緑風会を代表して、第1号議案、令和4年亀岡市一般会計補正予算(第3号)、第12号議案、令和3年度一般会計決算認定について、賛成の立場で討論します。 はじめに、令和3年度一般会計の歳入決算額は、432億5,191万9,000円で、5年連続、市税が100億円を超えています。 ふるさと納税、寄附金に関しても、32億521万3,989円と、今までの努力が実り、すばらしい結果となっています。 桂川市長が掲げられている、第5次亀岡市総合計画、人と時代に選ばれるリーディングシティ亀岡がスタートしました。 世界に誇れる環境先進都市の実現に向けた取組を進められ、全国に先駆けて、多種多様なチャレンジをされています。 重点テーマとしては「子育てしたい、住み続けたいまちへ」「スポーツ・歴史・文化・観光の魅力で産業が輝くまちへ」先ほどにも申しました「、世界に誇れる環境先進都市へ」「だれもが安心して暮らせる防災・減災、セーフコミュニティ、多文化共生のまちへ」「次代をリードする新産業を創出するまちへ」の5つのテーマがあります。 目指す都市像を実現していくために、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 9月には子どもファースト宣言を出され、話題になったばかりですが、子育てワンストップ窓口でありますBCome+の充実、妊娠期から切れ目のない支援などの推進、また、安定して職員が業務できるように取り組んでいかなければなりません。 新しい事業を始めるということは、非常に大切なことでありますが、リードばかりで中身が安定していない事業もあると考えられます。 しっかりと人材を補充し、育成する必要がある部署がたくさんあるように思われますので、持続可能な環境、経済、社会、安全・安心な暮らしを創造するためには、基礎づくりを、まさに土台づくりを構築していかなければなりません。 令和3年度産業建設常任委員会決算分科会では、指摘要望が5項目出されておりますが、農業担い手づくり育成事業で、家族営農に対しても、しっかりどのように支援をしていくのか、考える必要があります。 また、耕作放棄地をできるだけなくしていくためには、今後の重要課題の1つにもなると思われます。 次に、以前から大変問題視されています、亀岡市土づくりセンターの悪臭問題、この問題をどのように解決していくのかは、以前から進捗のないまま、近隣はもちろんのこと、広範囲で住民の方々に対して、かなりの迷惑をかけているのは事実であります。 いつになれば、前向きに取り組んでいただけるのか、スポットでは意味がありません。できるだけ早期に、住民の方々が安心して生活ができるよう、お願いしたいと思います。 次に、林業担い手育成事業経費について、分科会でも常に議論されている、これもまた最重要課題でありますが、豪雨災害などで、あらゆる亀岡市内の山林が倒木し、二次災害、三次災害へと進み、山場の斜面が崩れている地域もあります。 早急にプランナーを育てることが最優先であります。 亀岡市森林組合の組織改革、強靱化が必要になってきます。これは、以前から長々と問題になっていることであります。 以前から農林振興課職員は、真剣に、前向きに考えてくれていますが、なかなか担当職員1人でクリアすることは厳しい状況、限界があると思われます。市長、増員してください。市長の決断がない限り、この事業はなかなか進まないことが分かりました。 産業建設常任委員会では、視察や研修を重ね、森林整備につきましては、2年前から声や手も挙がっています。 これは、即刻進めなければ、災害が起きた場合、市民の大切な命が奪われてしまう可能性があり、現在も非常に危険性の高い地域がたくさんあると思われます。 来年度にはしっかり計画、プランナーを育成し、大幅な予算を投じていただきたい。 次に、商工業振興対策経費でのサンガスタジアム・イノベーション・フィールド実証支援事業ですが、実証実験だけで終わらないように、企業が残る仕組みを整えていかなければなりません。 企業が定着するか、しないかは、市長の政策判断に委ねられます。本当に期待しています。 次に、観光推進経費での川の駅・亀岡水辺公園につきましては、指定管理者の指導、また連携をしっかりしなくてはなりません。それ以前に、京都府にしっかりと予算を組んでいただくことも大切であります。 次に、総務文教常任委員会からは、4項目の改善点を申し上げます。 まず初めに、みらい教育リサーチセンター経費であります。市内の小学校1年生に、タブレットを全員配布しましたが、何と授業で使われていない学校があるということが発覚しました。 使用頻度に差があるということに関して、これは非常に問題があるのではないでしょうか。 小学校低学年での学びというものは、将来において非常に大切な時間であります。 通う学校やクラスによって、生徒の学びに差が生まれないようにしていただきたい。 学校、現場の先生方との連携は、大変必要になってきますので、ICT教育の推進はもちろんのこと、未来に羽ばたく子どもたちのために、学びの点には特に注意していただくようお願いいたします。 次に、パートナーシップ宣誓制度についてであります。 市長肝いりの施策であるにもかかわらず、審議中、今回、担当課長は答弁が不十分で、ほとんど部下に聞くレベルであり、非常に残念でありました。 誰もが住みやすいまちづくりにしていくためには、啓発活動はもちろんのこと、市民のためにもしっかり推進していただきたいと思います。 行政改革推進経費でありますが、まず、経費そのものよりも、行政改革推進委員会の会議そのものの進め方について、問題があると思われます。 市民公募で委員として参加されている、質問などもしっかり反映していけるような仕組みづくりを作らなければ、議論も深まらず、新しいまちづくりはできません。本当の行政改革を進めていくのであれば、改善していただきたいと思います。 次に、事務事業評価項目として挙げられたガレリアかめおか運営経費であります。 今後は、必ず深刻な問題になると思われる、ガレリアかめおかの指定管理料の件について、今年度の決算では、2億5,940万8,000円をつぎ込み、屋根の改修工事が終了いたしました。しかし、今後も長寿命化改修工事として、令和41年までにかかる費用が、積算ではありますが、120億円ほどかかるとのことであります。 今回から、指定管理が、公益財団法人から一般社団法人コンベンションビューローに替わりました。毎年の指定管理料は約2億円必要でありまして、これは公益財団法人時から約2億円は変わっておりません。この施設の目的は、利用者の利便性、満足度の向上を目指すということでありますが、毎年2億円を投入しているのにもかかわらず、年間の施設利用料が、コロナ前の3年間の収入平均で約6,600万円、約2億円の指定管理料を支出し、収入が約6,600万円です。このままでいいのでしょうか、 先ほどにも申しましたが、公共施設ということで、市民に使っていただくというのが目的でありまして、生涯学習、また公益の活動の拠点ということ、多くの方が喜んでいただいているのは分かります。 問題は、約2億円のうち、約1億円近くが人件費であることです。 これは大丈夫なのでしょうか。幾ら公共施設でも税金です。年間マイナス1億3,000万円の税金が失われている。もう少し真摯に考えるべきだと思われます。 ガレリアかめおかの職員の規律から、今後の施設の大幅な見直しも考え直さなければなりません。 また、当初から割れないと言われている、大きなガラスの修繕費についても、1枚約100万円かかるようなガラスでは、施設を維持していくのも非常に大変であります。 今後、市民の負担を考えると申し訳なく、心苦しい限りであります。 将来はガレリアかめおかの施設半分を民営化するなど、事業としても運営できる仕組みを考えなければなりません。 もう一度言いますが、約2億円の指定管理料を支払い、人件費が1億円で、しかも収入が約6,600万円。これは、市長自身が真剣に取り組むべきことであります。 事務事業評価では、見直しの上、継続とのことでありましたが、早急に見直していただきますよう、よろしくお願いいたします。 先ほどから申しますように、生涯学習施設ですが、全て税金です。 次に、環境市民厚生常任委員会では、環境保全対策事業経費、いまだに減らないポイ捨てや不法投棄、中山間部ではかなりのポイ捨てなどがあり、市街地のみの清掃活動では環境先進都市とは言えません。 焼却施設であります桜塚クリーンセンターの焼却炉の老朽化の問題、焼却炉の維持修繕を最大限に使い、修繕に莫大な予算が必要とされています。環境先進都市として、少し行動が遅く感じられます。 今後、ごみを削減する一番早い方法、焼却炉ができるだけ劣化しない方法とは、生ごみを減らす対策ではありませんか。お隣の韓国でも始めています。 スマート生ごみ回収箱。日本では千葉県市川市でも始められました。生ごみは水分が多いため、プラスチックごみを燃焼代わりに燃やさなければいけません。 そのため、どうしても焼却炉が高温になります。ぼろぼろになりやすいわけでありますが、早急に生ごみ対策を考えることによって、あらゆるごみ対策問題が解決していくように思われます。生ごみは、堆肥や動物飼料、バイオ燃料などにリサイクルでできることで、循環型経済にもつながりますし、廃棄処理のコストや、二酸化炭素の排出量も削減ができるため、市長が目指しておられます脱炭素社会に、一歩二歩、近づけるのではないでしょうか。 より一層、エネルギーの向上、有毒ガスなど、抑制ができる新技術も取り入れていかなければなりません。生ごみを資源、宝物にできるように考えていくのが、最優先課題だと思います。もし計画があれば、早急に進めるべきだと思われます。 次に、介護予防・日常生活支援総合事業経費の見直しについては、フレイル対策を検討するとのことでありますが、人は高齢になりますと、外出する機会が減るため、体力が落ちてきます。手助けや介護が必要になってくるのは承知のとおりで、虚弱体質になる状態がフレイルということですが、これからの時代は、自立して日常生活が送れるような環境を整えていかなければなりません。 このフレイル予防は、健康寿命を1日でも延ばす、すばらしいことであります。 超高齢化社会の今、最重要課題ではないでしょうか。長寿に必要なのは栄養、運動、社会参加、この3つの柱をどうつなげるか、どうリンクしていくかが大切であります。コロナ禍で社会のリズムが崩れてしまい、コミュニティが減少、この減少を打開するためには、亀岡市として、手厚い、思いやりのある事業を真剣に考えていただきたいと思います。 次に、第1号議案、令和4年亀岡市一般会計補正予算(第3号)であります。 まず、民生費、保育園などの紙おむつの無償提供・回収事業については、保護者の負担軽減になったということで、非常に温かい補正となっていますが、今後事業を進めるためには、各保育所などに十分理解してもらえるよう、協議を重ねていただき、また、各家庭で使用されているメーカーやこだわりもあると思われるため、正確に聞き取り調査をし、具体的にどう対処していくのか、協議しながら進めていただきたい。 また、布おむつを使用されている家庭への配慮も必要になってきます。 布おむつには補助金がなく、対象外なのは残念で仕方ありませんが、個人が選択できるよう、布おむつが使用できるような仕組みをお考えいただけると、非常に助かるのは市民の方でありますので、配慮をよろしくお願いいたします。 商工費では、JR亀岡駅にあります、非常に入りづらいと言われておりました、観光案内所の大幅な改修工事が行われます。亀岡の名産や観光の情報拠点として進めていかれるのを期待しております。 また、新しい指定ごみ袋製作業務経費につきましても、細かく分別ができる細分化、これをどのような仕組みにしていかれるのか、注目していきたいと思います。 その他、総務費から始まり、農林水産、土木、教育費まで、市民の要望にしっかり応えられている内容になっております。 来年度からは、予算編成につきましては、計画的に行っていただき、各部署から整合性などを正確に聞き取り、無駄な経費がないか、予算漏れがないかなどをしっかりと精査し、スクラップアンドビルドも視野に入れ、財政が健全な今、なおしっかり拡充した道路行政、子育て支援からお年寄りの見守りまで、よりよいものにしていただくよう、お願いいたしまして、賛成討論とします。 |
|
私は、新清流会を代表して第12号議案一般会計決算認定に賛成の立場で討論いたします。 令和3年度は、市民力で未来を拓く!「健康・環境・観光・多文化共生のまち亀岡、世界に誇れる環境先進都市の実現」をスローガンに、第5次亀岡市総合計画スタートの年として「人と時代に選ばれるリーディングシティ亀岡」の実現に向け、対前年度比10.4%の増額予算が編成されました。 依然として、コロナの終息が見えない困難な中、市税の歳入においては当初想定していた税収の落ち込みもなく、対前年度比0,4ポイントの増額となり5年連続で100億円を維持されております。またこれまでも着実な伸びを示してきた、ふるさと力向上寄付金も大きな増収となり、31 億円を超えるなど、財源の確保に努められてきました。 令和3年度決算における実質収支は17億8,479万円で、市政施行以来、最大の黒字額となりました。 また、実質公債費比率は12.9%で前年度と比べると0.4ポイントの改善、将来負担比率においては75%となっており、こちらも前年度より14.9ポイントの改善が見られます。 歳出面においては、引き続いてのコロナ対策をはじめ、課題山積する中において、堅実かつ計画的に市民福祉の増進に向け事務事業執行が進められてきたところです。 さまざまな事業の中でも5つの重点施策として、子育てしたい住み続けたいまちへ!については、子育てひろば場事業として、ガレリアかめおかに整備されたかめおかっこ広場や青空広場等は本市内外からの利用も多く、中でもかめまるランドにおいては令和3年度の来場者が38,739人と、令和2年度の13,838人から大きく増加したことは子育て世代に大きく支持されたことが要因であると推察できます。 こども宅食事業においては、当初の利用者から増加傾向にあり、延べ1,533件の利用と拡大、長期化するコロナの影響も大きく懸念がある中、今後も見守りを必要とする世帯を孤立化させることなく、常に寄り添う事業として今後の成果に期待するところであります。 また、世界に誇れる環境先進都市へ!では、環境にやさしいまちづくり推進経費における第3次亀岡市環境基本計画の策定、プラスティック製レジ袋に代わる代替紙袋の購入補助事業をはじめ、かめおか保津川エコツアーの実施など環境と経済の一体的な取組みが行われました。 次に、次代をリードする新産業を創出するまちへ!では、コロナ禍における非接触型の販売形態である、移動販売設備(キッチンカー)導入支援事業におけるキッチンカー購入費や調理什器導入に係る改修費等で1,179万2千円、この補助事業については、延べ18件の利用があり、今後の商工振興ならびに商工発展に大きく期待するものであります。 今後はさらに導入支援を受けたキッチンカー事業者が事業継続できるよう本市で開催される事業やイベントにおいて出店の機会の提供や担当所管におかれては強力なサポートを望むところであります。 このようにコロナ対策をはじめ、課題が山積する中において着実にかつ計画的に市民福祉の増進に向けた事務事業執行が行われて来たところであります。 今後はまさに子どもファースト宣言の各事業推進により、魅力的な亀岡市としてのまちづくりが進められる事に大きく期待し、第12号議案令和3 年度亀岡市一般会計決算認定の賛成討論とします。 |
|
私は、公明党議員団を代表いたしまして、第12号議案、令和3年度亀岡市一般会計決算認定について賛成の立場で討論を行います。 令和3年度一般会計予算は、第5次亀岡市総合計画元年であり、スタートダッシュの予算として、人と時代に選ばれるリーディングシティ亀岡実現に向け、前年度比10.4%増となる364臆6800万円の積極的予算を編成されました。 一般会計歳入決算額は、45、120、565千円で、前年度に比べ2,208、217千円4.7%減少、主な要因は新型コロナ対策の国からの依存財源が減少し、国庫支出金38.1パーセント減の5,968,393千円、府支出金6.6パーセント減226,909千円であります。 しかし、自主財源の根幹とする市税収入は100億円を確保し、市税全体で0.42%増の10,082,350千円でした。 また、寄付金については、ふるさと納税についても返礼品の充実や様々なデジタル広告を総動員させ、情報強化に努められた結果、前年度の約1.3倍増加し3,105,592千円を確保されました。 市の財政状況を安定させるための自主財源確保のたゆまぬ努力を高く評価するところであります。 一方、一般会計歳出決算額は、43,251,919千円で、前年度に比べ3,288,938千円7.1パーセントの減少です。 最終令和3年度一般会計決算内容は、形式収支が1,868,646千円、実質収支が1,784,793千円の黒字決算を計上しました。しかしながら、弾力性を示す経常収支比率においては、94.4%から89.4%と、改善が見られますが、まだ高い水準であり引き続きの警戒が必要です。 今後も、限られた財源を効果的、効率的に活用し、より多くの成果が収められるよう、引き続きよろしくお願いいたします。 次に、人と時代に選ばれるリーディングシティ亀岡の実現に向け、主な施策を3点申し上げます。 一つ目として「活力あるにぎわいまちづくり」では、サンガスタジアム・イノベーション・フィールド実証支援事業やウィズコロナの地域経済展開策としてキッチンカー導入支援を実施されました。 この事業は、時代の変容に沿った働き方を応援するものであり、導入により独立に踏み込まれ、挑戦を継続された若者経営者などの活気やお声を多く見聞きし、今後はでき得る限りの販路支援を求めるところです。 さらには、継続事業として地域経済活性化雇用進出を図る企業立地等奨励事業でありますが、今後建設される篠町篠企業団地内の地元雇用枠が増え、非正規雇用などの社会的弱者や子育て世代などの雇用創出につながり、地域の発展に寄与することを、大いに期待致します。 二つ目は、子育て、福祉、健康のまちづくりでは、こども宅食事業を実施されました。 子どもの育ちの見守り強化として重要な事業であり、引き続き見守りの質を上げ、安心して子育てできる体制を強化し、子どもの虐待防止や子どもの貧困などの課題解決の糸口につなげていただきたいと思います。 ひとり親などの増加により、以前にも増して社会的弱者の多様化が進んでいます。 弱者を支援する事業として、さらなる強化をよろしくお願い致します。 また、豊かな学びの確保として、みらい教育リサーチセンター創設事業を実施されました。 ICT機器を活用した推進や適応指導教室の拡充を図られました。 特に、コロナ禍の中、小・中学校における不登校児童数の増加に伴い、子どもの状況に合わせた授業のカリキュラムを組める体制など、誰も置き去りにせず、一人一人がしっかり学んでいける環境整備の司令塔として、みらい教育リサーチセンターが機能することを大いに期待しています。 福祉部門においては、複合的かつ複雑化した課題解決できる住みやすい体制構築として、重層的支援体制整備事業への移行準備事業を果敢に取り組んでいただいております。 令和6年度からの本格実施に向け、確実に事業を練り上げ、コロナ前から指摘されていた経済的格差の拡大や社会的孤立によるひずみに光を当てる取組へと、包括的に四方へ広がることを期待しています。 三つ目として、環境先進都市づくりとして令和4年度以降の環境の基本計画となる第3次亀岡市環境基本計画を策定されました。 令和3年度においては、亀岡市立小・中学校全校にウォータサーバーを設置していただき、学校環境の向上に努められました。今後も、亀岡市環境基本計画に基づき、ごみ減量、資源化を確実に進め、令和4年度に引き継がれる環境政策発信交流拠点でありますが、環境先進都市にふさわしい、既存の施設にない、環境の想いが凝縮され次世代に誇れる施設整備ができることを大いに期待し、今後も市民、企業協働で環境先進都市のまちづくり構築にまい進していただきたいと思います。 以上を、令和3年度決算の中で、主な事業として取り上げさせていただきましたが、おおむね適正に事業を実施していただき、評価致します。今後も、感染症の長期化や物価高騰、自然災害の激甚化など、先行き不透明による市政運営が続くであろうと予想致しますが、各決算分科会審査過程で出されましたご意見に、ご配慮いただき、市政運営の健全化を維持していただきたいと思います。 重ねて、今後もクオリティな発想を取り入れ、時代の変化に呼応した桂川市長の手腕を大いに発揮し、進化し続ける市政運営へ導いていただくことを強く念願致します。 公明党会派も、多様な民意を拾い、人と時代に選ばれるリーディングシティ亀岡の実現に向け、尽力する事をお誓いし第12号議案、令和3年度一般会計決算認定についての賛成討論とします。 |