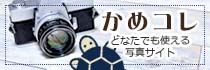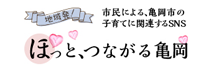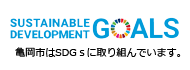ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
アユモドキとは
アユモドキとは?
どんなサカナ?
アユモドキは、名前のとおり泳いでる姿がアユに似ているところからこの名前が付けられた、コイ目アユモドキ科の淡水魚です。
口ひげが3対あり、2対は上あご先端に、1対は口の後端にあります。
その他の特徴としては、頭と胴部が側偏し、尾びれの後縁に深い切込みがあり、背から体側部は黄褐色で腹部が乳白色。幼期には体側に明瞭な暗褐色の太い横帯(シマ模様)がみられます。
体長は、大きくなると15cm程度になります。
野生に生息しているアユモドキの寿命は、概ね3年~4年と考えられています。
絶滅が心配されています。
- 京都府レッドデータブック 絶滅寸前種 平成14年(2002)
- 環境省レッドデータブック 絶滅危惧IA類 平成15年(2003)
- 国際自然保護連合(IUCN)レッドリスト 絶滅危惧種(CR) 平成27年(2015)
法律・条例などで守られています。
- 文化財保護法に基づく 天然記念物 昭和52年(1977)
- 種の保存法に基づく 国内希少野生動植物種 平成16年(2004)
- 京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例に基づく 指定希少野生生物 平成20年(2008)
許可なく捕獲・殺傷すると
- 文化財保護法 5年以下の懲役若しくは禁固、または30万円以下の罰金
- 種の保存法 5年以下の懲役、または500万円以下の罰金

どんなところにいるの?
亀岡市では、保津川(桂川)とその支流河川に生息しています。
亀岡市の田んぼ(水田)では生息していませんが、農繁期に稚魚の一部が農業用水路に遡上することがあります。
どうしていなくなったの?
昔、アユモドキは琵琶湖淀川水系の河川のあちこちで見ることができましたが、現在は、岡山県と亀岡市でしか見られなくなってしまいました。
- 治水対策の進捗などにより、産卵場所に適した一時的水域(氾濫原環境)の減少
- 外来魚(オオクチバスやブルーギルなど)の侵入による食害
- 農業の手法の変化や圃場整備、河川整備などによる生息環境の変化
などが原因とされています。
亀岡市で生き残った理由
専門家により、平成15年度からはじめられたアユモドキの調査の結果、アユモドキは川の増水などにより生じる一時的水域でしか産卵をしないことがわかってきました。河川の整備が進み、そうした場所がだんだん少なくなってきました。
- 現在の生息地では、農業用のラバーダムが立ち上がることで、人為的に氾濫原環境が作り出され、奇跡的にアユモドキの産卵・繁殖環境が守られてきました。
アユモドキが増えない理由
- ラバーダムの立ち上げで産卵しても大雨が降ると、卵や仔稚魚が流されてしまいます。

大雨の影響で増水した様子(平成26年8月)
- 上流のため池などからオオクチバスなどが侵入し、アユモドキが食べられてしまいます。

アユモドキを食害するオオクチバスを駆除

やな漁による外来魚駆除活動