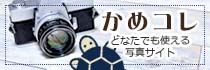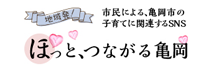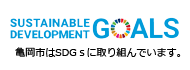本文
モビリティ・マネジメント(MM)に取り組んでいます
モビリティ・マネジメント(MM)とは
モビリティ・マネジメント(MM)とは、渋滞や環境、あるいは個人の健康などの問題に配慮して、過度に自動車に頼る状態から公共交通や自転車などを『かしこく』使う方向へと自発的に転換することを促す取り組みを意味します。亀岡市では以下のようなモビリティ・マネジメントを行っています。
市役所におけるエコ通勤の実施
市役所では自発的な交通意識の変革を促し、通勤時における自動車利用を削減するために、毎月第2・第4水曜日をできる限り車の使用を控える日とし、その日を「エコ通勤デー」と定め、職員で取り組んでいます。
エコ通勤の取り組みにより、燃料使用量およびCo2排出量を減少させることができています。通勤の際には積極的に公共交通機関を利用して、引き続きエコ通勤に取り組みます。
お得にバスを利用できるサービスが開始されました!
- ICOCAポイントサービスのご案内<外部リンク>
小学校における交通環境学習の実施
亀岡市では、市内の小学生を対象に地元の事業所にご協力いただき、平成23年度から『交通環境学習』を実施しています。公共交通を通じて、自分たちの住んでいる地域や環境問題、まちづくりについて気づき、考え、学ぶきっかけづくりを行っています。
令和6年度
大井小学校(令和6年12月16日実施)~バスについて学ぼう、公共交通の福祉の取組について~
1年生、4年生を対象に、京阪京都交通(株)の協力のもとバスを学校へ持ち込んでいただき、バスに関する学習を行いました。
1年生は、「バスについて学ぼう」と題して、バスには乗車する人に配慮した工夫がたくさんあることや、環境に優しい乗り物であることを学びました。また、4年生は、「公共交通の福祉の取組」について、これまで学習してきた福祉の内容とも関連付けて、路線バスが学校や病院、駅などを通っていて、だれもが利用できるための工夫がされていること、運転士不足や利用客の減少により、継続が難しくなってきていることなどを知ってもらいました。
教室での学習の後は、実際にバスの乗車体験を行い、運賃の支払い方やバス車内の工夫について学び、バスに対する興味を持っていただくきっかけとなりました。
児童・保護者の感想(抜粋)
- けがしたり、妊娠している人の椅子があるんだと思いました。
- バスは色々なことに注意されて、安全に走れるんだと思いました。
- 最近全然乗ってなくて、バスが無くなったら困るので、これからは出かける時とかに乗ろうと思いました。
- バスの運転士が足りないということにびっくりしました。
- 家族や知っている人にもバスの魅力を伝えたいです。
- 移動は基本車ですることが多いので、これを機会にバスや電車を使ってみようと思います。(保護者)
- 学校の外に出て、世の中のことを知れるきっかけになったり、他人に配慮しようという思いが芽生えたり、子供達にとって貴重な体験だと思います。(保護者)
令和5年度
大井小学校(令和5年6月7日,6月28日実施)~ふるさとバス並河駅コースの赤字を減らすには?~
「ふるさとバス並河駅コースの赤字を減らすには?」をテーマに、市民福祉の向上に重要な施策であるバス交通を通じて、市の役割や仕組みを学び、まちづくりに関心を持ってもらう機会としました。
アイデアとしては、「バスにイラストを描く」、「料金を安くする・高くする」、「バス停を増やす」など数多くの提案が出ました。また、バスを利用する人と税金で赤字を負担する人の立場や様々なまちづくりに税金が使われていることを学びました。
児童・保護者の感想(抜粋)
- 1回の料金を上げたらいいと考えていたが、今日の話を聞いて、上げたら乗る人も減るかもしれないということに気づいた。
- ふるさとバスは約700万の赤字があることが分かったときは驚いた。同時にどうにかしなければならないと思った。
- webサイトや広告をやるのはいいと思ったけど、見にくいなどの批判もあって色々難しいんだなと思った。やはり料金を安くしてたくさんの人に乗ってものらえるようにするのがいいと思う。
- バスは二酸化炭素の排出量を減らしたり免許がなくても乗れたりできることを知った。
- 車社会でついつい車を使いますが、車を運転しない若者、子供達や高齢者にとってもなくてはならない交通の便を守っていただきありがとうございます。特に田舎は交通の便が悪くなるとさらに過疎化が進んでしまうためよろしくお願いします。(保護者)
- 子供を通じて、取組みを知ることができてよかった。幅広い住民の声をこれからも反映させていただけることを願います。(保護者)




令和4年度
大井小学校(令和4年6月13日実施)~ふるさとバス並河駅コースの赤字を減らすには?~
「ふるさとバス並河駅コースの赤字を減らすには?」をテーマに、市民福祉の向上に重要な施策であるバス交通を通じて、市の役割や仕組みを学び、まちづくりに関心を持ってもらう機会としました。
アイデアとしては、「時刻表の文字を大きくして、お年寄りが見やすくする。」、「料金を高くする。」、「バスの利用目的(通勤・通学や土日祝日)に合わせて運行時間を管理する。」など数多くの提案が出ました。また、バスを利用する人と税金で赤字を負担する人の立場や様々なまちづくりに税金が使われていることを学びました。
児童・保護者の感想(抜粋)
- ふるさとバスが必要な人や必要でない人の意見を聞きながら、市役所の人が上手にアイデアを考えながら取り組んでいたので、すごいと思った。
- バスのルートを増やしたらいいと思っても、その費用がかかることを考えてなかったから、アイデアを考えるのも大変だなと思いました。
- 亀岡に住んでいる人は、よく車で移動しているが、車は二酸化炭素を多くだすので地球に悪いと調べてわかった。
- ふるさとバスが走り続けるためには、利用しやすい工夫やターゲットに合ったことをして赤字を減らすことが大切だと思う。
- 車での移動ばかりで、ふるさとバスの存在を知らなかったようです。逆に車での移動が難しい人たちにとってのバスの存在を一緒に考えました。(保護者)
- 祖父、祖母の家がふるさとバスの経路にあるため、よく利用しています。交通弱者にとっては、とても重要なものとなっているのでなくさないでほしいです。(保護者)



令和3年度
詳徳小学校(令和3年6月11日、7月2日実施)~バスの利用者を増やすためには?~
「バスの利用者を増やすためには?」をテーマに、アイデアを考えることを通じて自分たちの暮らしている地域にとって大切な交通手段であるバス交通について学びました。
6月13日の市民ノーマイカーDayの日には多くの児童がバスに乗車し、バス停で時刻を調べるなど身近なものとして関心を持ってくれました。
また、税金や予算など実際に市議会で議論されているDVDを視聴して、市役所の役割からまちづくりについて学びました。
児童の感想(抜粋)
- バスに興味を持てたのでもっと調べてみたいです。
- お金を儲けるためではなく、バスを利用する人のことを考えていることがわかった。
- 予算を決めるまでには、市長や市議会まで提出しないといけないことが大変だと感じました。


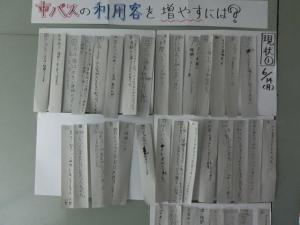
令和元年度
青野小学校(令和元年12月4日実施)~バスについて学ぼう!~
「バスについて学ぼう!」をテーマに、今回も京阪京都交通(株)の皆さんにバスを持ち込んでいただき、バスについて学びました。
バスには乗車する人に配慮した工夫が多くされていること、環境に優しい乗り物であることを説明し、また、乗車体験を通して、車いすでのバスの乗り方や運賃の支払い方法などを学びました。
日常の移動は自家用車が多く、公共バスに乗る機会が少ないという児童が多かったため、実際に市内を走行するバスに触れることができ、興味関心を持つきっかけとなりました。
児童の感想(抜粋)
- バスのドアが閉まっていても運転手と話ができるので驚いた。
- 車いす用の場所があることや固定するベルトがあることを知った。
- バスに乗れて楽しかった。



平成30年度
吉川小学校(平成30年12月5日実施)~バスについて学ぼう!~
「バスについて学ぼう!」をテーマに、バスはすべての人が乗りやすいように工夫がされていることを説明し、人にも環境にも優しい乗り物であることを学びました。
今年は京阪京都交通(株)の皆さんにバスを持ち込んでいただき、車いすでの乗降体験、車外のインターホンを使った乗務員との会話体験、車内にたくさんある鏡の役割や優先席の意味などを説明してもらいました。
また、模擬乗車を行い、時刻表やバスの行先表示の見方、距離に応じて運賃が変わることや運賃の支払い方を学びました。
児童の感想(抜粋)
- バスの中にたくさん鏡があることを知らなかった。
- 車椅子の人がバスに乗るためのスロープが入口近くにあることを知った。
- バスの乗り方が勉強できてよかった。



平成29年度
安詳小学校
【第1回目】市のしくみについて学ぼう!(平成29年11月27日実施)
「市のしくみについて学ぼう!」をテーマに、自分たちの住むまちについて考えました。
市の予算を決めるまでにはさまざまな工程があること、決められた予算はどのように使われるのかなど、市役所の仕事を通じて市のしくみを学びました。
また、篠地区コミュニティバスが走る安詳小学校では、バスの利用者を増やすためにはどうすればいいのか、児童のみなさんからさまざまなアイデアが寄せられました。
寄せられたアイデアを受けて、実際に市が取り組んでいる事業についても紹介し、より理解を深めました。
児童の感想(抜粋)
- 市の予算はよく考えて決められていることがわかった。
- 市役所のしくみや目的がわかった。
- コミュニティバスについての考え方がかわった。
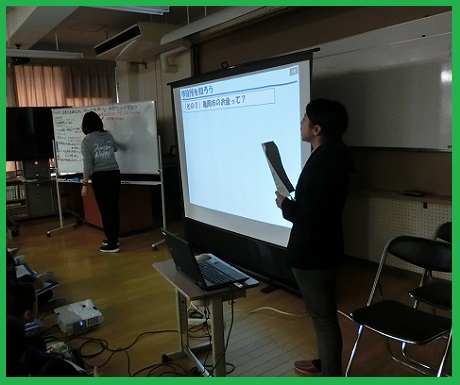

【第2回目】篠地区コミュニティバスについて(平成29年12月6日実施)
第1回目での学びを受けて、現在試験運行中である篠地区コミュニティバスについて、本格運行に賛成あるいは反対の意見を児童のみなさんが根拠を示しながら発表してくれました。
自分たちの住むまちを運行するバスについて、児童の目線からさまざまな意見が挙がりました。
児童の意見(抜粋)
- コミュニティバスは市民のために走っていることがわかったので、本格運行してほしい。
- バスは利用しないし、運行にも経費がかかるため、本格運行の必要はない。
- 最初は本格運行に反対であったが、いろんな人から話を聞いて賛成に変わった。

今回の交通環境学習では、児童のみなさんがバスについて調べたり、人に尋ねたり、とても積極的にバス交通について考えてくれました。
市内を走るバスを通じて、自分の住むまちのしくみや取り組みについて関心を持つきっかけとなりました。
平成27年度
大井小学校(平成27年11月12日実施)~物流の工夫を知って、みんなの交通を考えよう!!~
工業団地の近くにある大井小学校では、工場にどのように原材料が運ばれ、完成した製品がどのように出荷されていくのか、物流を支えるトラックの働きから交通を考える学習を行いました。
ヤマト運輸(株)の皆さんの協力のもと、普段、配送で使われているディーゼル車や電気自動車、新スリーター(リヤカー付き電気自転車)をグラウンドに持ち込んでいただき、各車両の特徴や環境に配慮されていることを教えてもらいました。また、私たちが荷物を預けてから受け取るまでは、コンピューターで管理されていることをイラストを交えて分かりやすく解説してもらいました。
物流にはトラックなどの車は欠かせないものですが、さまざまな工夫で人にも環境にも優しい取り組みがされていることを学びました。
児童たちの感想から
- 地球温暖化を防ぐために、自分たちにもできることがあるので手伝いたい。
- クロネコヤマトの人も環境に良いことを考えていることが分かった。
- できるだけ車を使わず、歩きや自転車、電車、バスを使って移動したい。
南つつじケ丘小学校(平成27年12月17日実施)~南つつじケ丘を走るバスを知ろう!~
「南つつじケ丘を走るバスを知ろう!」をテーマに、バスの時刻表から朝夕の通勤・通学の時間帯と昼間のバスの本数の違いやバスと電車の時刻には関係があることを学びました。
今年も京阪京都交通(株)の運転手さんたちにバスを持ち込んでいただき、車いすに対応したスロープやたくさん付いている鏡の役割などを説明してもらいました。みんなが安全に安心して乗ることができるように、いろいろな工夫がされていることを知りました。
また、「バスの利用者が減るとバスの本数が減る。バスを使うことはバスを大切にすること」と、話していただきました。地域のバスや公共交通について学び、自分たちにできることを話し合いました。
児童たちの感想から
- バスにはいろいろな機能があった。非常出口には驚いた。
- バスがなくならないように、買い物にはバスで行きたい。
- バスに乗ったときはマナーを守り、他の人に迷惑を掛けない。
川東小学校(平成27年12月18日実施)~川東を走るバスを知ろう!~
5回目となる今回も京阪京都交通(株)の皆さんに協力をいただき、バスを学校に持って来てもらいました。
運転手さんが安全に走るための工夫や運転席周りの機械について説明すると、熱心にメモをとる姿が見られました。普段はなかなか見ることができない非常用出口を開けてもらったり、バスの後ろにあるエンジンを見せてもらうと、みんな驚きの声を上げていました。
川東小学校では児童の半数が通学にバスを利用していますが、今まで知らなかった新しい発見がたくさんあったようです。バスは環境に優しく地域を支える大切な乗り物であることを学び、毎日の通学からバス交通を考えるきっかけになりました。
児童たちの感想発表から
- バスには人にやさしい工夫がいっぱいあった。お母さんにも教えてあげたい。
- バスには鏡がいっぱい付いていた。一つ一つが大切だと分かった。
- 平日と休日ではバスの本数が違うことが分かった。
かめおかばすまっぷ

バス交通の利用促進に向けた取り組みとして、「かめおかばすまっぷ」を作成しています。
市役所、JR亀岡駅観光案内所、京阪京都交通(株)などにマップを設置しているほか、亀岡市へ転入された方には「転入届」の受付窓口で配布しています。
バスは、環境にやさしく地域に欠かせない乗り物です。