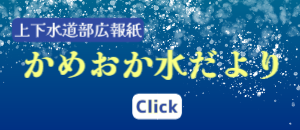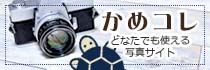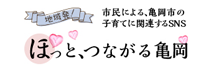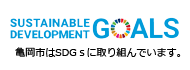ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
令和3年度第2回亀岡市上下水道事業経営審議会審議概要
1.開催日時
令和3年11月25日(木曜日)午後1時から3時10分まで
2.開催場所
亀岡市上下水道部3階301会議室
3.出席者
委員9人(学識経験者4人、公益代表3人、需要家代表2人)
4.次第
- 開会
- 会長あいさつ
- 部長あいさつ
- 協議事項
水道加入金・下水道受益者負担金制度のあり方について - 閉会
5.審議内容(主な意見)
会議全体を通しての主な意見は次のとおりです。
水道加入金・下水道受益者負担金制度のあり方について
- 水道加入金・下水道受益者負担金は、負担する主体が異なる場合があり、事業者が過重な負担を負っているとは必ずしも言えない。また、制度面と財政面で課題を分けて整理をしていくべき。
- 水道加入金のうち面積加入金を見直すのは良いとは思うが、すでに支払った人と今後支払わなくていい人との間の公平性について慎重になるべき。
- 口径加入金を採用している自治体は多いが、面積加入金を採用している自治体はほとんどない。水道加入金制度を見直すのは良いが、廃止して減収となり経営に影響するなら、加入金制度自体は存続させるべき。
- 一般市民にとってわかりにくい制度のため、見直す際はわかりやすく広報すべき。水道加入金制度を見直して減収となれば、水道料金の値上げにつながり、一般市民にも影響が出ると思われる。水道料金制度も併せて考えるべき難しい問題である。
- 資料の中で、水道加入金制度の見直しに伴う収入額の比較をされているが、上下水道ビジョンの数値と見直し案により算出した数値の基準時点が異なっているため、比較しづらい。
- 今後、大規模開発が見込めない状況で、面積加入金に頼ると収入が激変するので、使用水量のみに応じた加入金制度へと見直し、安定的な収入を確保するという理屈ならば理解できる。一般市民からの反発もそれほどないと思われる。
- 下水道受益者負担金制度を採用した以上、下水道事業を続ける限り、制度を廃止する根拠はないと思う。下水道の未整備箇所はまだ少し残っているので、制度を廃止するならばしっかりとした理由がないといけない。
- 今後、大規模開発が見込めないから受益者負担金制度を廃止するというのは理由にならない。宅地に転用できるような田畑がもうないのであれば制度を残す必要性がなく、廃止してもよいかもしれないが、まだそのような田畑があるならば制度を残しておくべき。
- 工事負担金は事業者が負担するが、下水道受益者負担金は事業者が一旦負担したとしても土地の価格へ転嫁することができるため、下水道受益者負担金は工事負担金とは性格が異なる。
- 下水道受益者負担金が減免される基準がわかりにくい。減収するならば、下水道使用料にどう影響がでるのかを示してほしい。
- 上下水道部門としては、あくまで事業者から下水道受益者負担金を徴収すべき。減免の理由がまちづくりの振興であるならば、一般会計側が奨励金などで事業者に補填すればよいと思う。特定の事業者のみ減免するのは、下水道の使用者全体に対して説明がつかない。
- 下水道受益者負担金を減免された事業者が、土地の価格に下水道受益者負担金分を転嫁するという事例が出てこないか。
- 水道加入金・下水道受益者負担金制度自体がわかりにくい制度であり、制度見直しの内容もわかりにくいので、委員の意見を踏まえてわかりやすい内容に修正してほしい。
【審議会の様子】

【審議会資料】