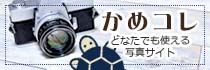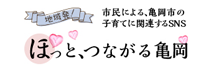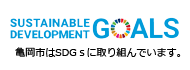本文
亀岡市と犬の関わり
亀岡市と犬の深いつながりをご紹介します
京都府内でも有数の犬の飼育率を誇る亀岡市。
多くの市民が愛犬との暮らしを楽しんでいます。
実はその関わりは古代にまでさかのぼります。
犬×亀岡市の関係がわかる3つのエピソードをご紹介します。
「日本書紀」に残る日本最古の飼い犬・足往(あゆき)

奈良時代に成立した歴史書「日本書紀」には、亀岡市にいた飼い犬の記録が残っています(垂仁天皇87 年2 月5 日条)。
記録として残る日本最古の飼い犬の名前は、「足往(あゆき)」。
丹波国桑田村(現在の亀岡市域)の住人・甕襲(みかそ) が飼っていた犬で、ある日、足往は山の獣を倒し、そのお腹の中から勾玉が出てきたという伝承が残されています。
このほか、亀岡市内には「犬飼(いぬかい)」や「犬甘野(いぬかんの)」という地名があります。
これら「犬」のつく地名は、番犬や猟犬を用いて大和政権の直轄地を守っていた官職「犬養部(いぬかいべ)」と関連があると考えられています。
はるか昔から、ここ亀岡の地では犬と飼い主がともに暮らしていたことが伺えます。
円山応挙-時代を超えて愛される狗子図-

円山応挙作「狗子図」。
安永7年(1778)、応挙46歳の作品。
敦賀市立博物館蔵
江戸時代中期~後期の絵師・円山応挙(まるやま おうきょ)は、丹波穴太(現在の亀岡市)の農家に生まれました。
応挙は京都で石田幽汀に師事して狩野派の絵画を学んだのち、写実を重視した新様式を確立し、円山派の祖となりました。
応挙は生涯、風景、動物、幽霊などさまざまなモチーフを描きましたが、なかでも人気なのが「犬」の絵です。
写実的で毛のやわらかさまで伝わってきそうな仔犬たちの絵からは、応挙が大の犬好きだったことが感じられます。
円山応挙
享保18 年(1733)~寛政7 年(1795)丹波穴太村の生まれで、京都画壇の源流・円山派の祖となり、三井家をはじめとした豪商のほか大衆に広く愛されました。
国宝「雪松図屏風」(三井記念美術館蔵)や、「保津川図屏風」(株式会社千總蔵)などが有名です。
ゆかりの寺「金剛寺」

円山応挙が生まれた穴太地域にある臨済宗天龍寺派の寺院。
応挙が8~15 歳の間に小僧として生活した寺といわれ、当時の住職玉堂和お尚(ぎょくどうおしょう)に絵を学んだといわれています。
のちに応挙は金剛寺の本堂全面の襖と壁56面に「山水図」「波濤図(はとうず)」「群仙図」を描いて寄進しました。
金剛寺 DATA
正応2年(1289)、仏国国師が開いた寺院。
鐘楼を兼ねた山門は江戸時代の建立です。
- 亀岡市曽我部町穴太宮垣内43
- 午前9時~午後4時
- 0771-22-2871
- 本堂内観覧を希望の場合は要問い合わせ。
毎年11 月3 日に国重文「波涛図(復刻8 襖)、同「群仙図」12 幅を特別公開。
※「山水図」「波濤図」は、東京国立博物館に寄託。
関西盲導犬協会-「盲導犬クイールの一生」の舞台は亀岡市-
テレビドラマや映画にもなった「盲導犬クイール」。
そのクイールが立派な盲導犬になる訓練を受けた関西盲導犬訓練センター(関西盲導犬協会)が、亀岡市にあります。
関西盲導犬協会は昭和55 年(1980)に盲導犬育成普及を願う京都府民によって設立され、盲導犬の貸与や育成、盲導犬ユーザーのフォローアップなどを継続的に行っています。
京都府内唯一の盲導犬育成施設で、豊かな自然に囲まれた敷地の中に訓練犬たちが暮らす「木香テラス」がたたずんでいます。
一般の見学については、毎月開催の見学会時に受け付けています。
実際のクイールの写真。
ユーザーと過ごしたあと、盲導犬のPR のため全国の小学校などを訪れ、活躍しました。
浅野美樹さん (公益財団法人関西盲導犬協会)

当協会は、京都府で唯一、盲導犬の育成・貸与を行う団体です。
亀岡市内をはじめ多くの方々から、寄付やボランティアなどの協力をいただいています。
人間にとって犬は、強い絆で結ばれたパートナーとなりえる特別な存在です。
ぜひ皆さんも、亀岡での犬との暮らしを大切に、愛情を育んでいってください。
協会 DATA
- 亀岡市曽我部町犬飼未ケ谷18-2
- 午前9時~午後6時
- 0771-24-0323
- 毎月開催の見学会はホームページをご確認ください。
関西盲導犬協会公式ホームページ<外部リンク>