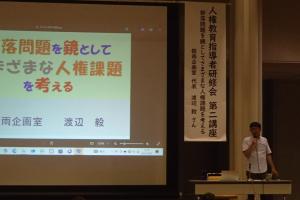本文
令和7年度研修
研修講座のお知らせ
- 令和7年度2・3月講座 [PDFファイル/138KB]
- 令和7年度1月講座 [PDFファイル/173KB]
- 令和7年度11月講座 [PDFファイル/370KB]
- 令和7年度10月講座 [PDFファイル/383KB]
- 令和7年度7・8月講座 [PDFファイル/378KB]
- 令和7年度6月講座 [PDFファイル/477KB]
- 令和7年度5月講座 [PDFファイル/344KB]
- 令和7年度4月講座 [PDFファイル/263KB]
研修講座の様子
亀岡のICT教育推進講座Ⅲ<1月20日実施>
近畿大学附属小学校 外山宏行様にお越しいただき、「アウトプット型情報活用能力の育成について ~調べて終わらない授業デザイン~」と題して、インプット以上にアウトプットを豊かにすることを中心にお話しいただきました。児童生徒の主体的な学びにつながるための「選択肢」などのキーワードや、端末の効果的な活用など、各所属でも広められる内容でした。また、参加者が講座での学びや気づきをスライドに表し、お互いが共有できる場ともなりました。



亀岡の学力向上講座Ⅲ
(第3回学力担当者会議)<1月19日実施>
今回も関西大学文学部岩﨑保之教授をお招きし、保津小学校から「かめ学サイクル」、東輝中学校から「ファシリテーション」についての実践発表の後、岩﨑教授にファシリテートをお世話になり、各校のレポートを基にした学力向上の1年間の取組の共有および来年度に向けて解決したい課題や、重点化した取組についてのグループ別ワークショップを行いました。最後に、岩﨑教授からは学力向上には亀岡の「確かな学力育成ビジョン」に基づく取組が大切であること、「問いやゴールを明確に示す」授業づくり、子どもたちの協働による学びの深化・統合の重要性について指導助言いただきました。



新規採用教職員講座<1月15日実施>
今年度新規採用教職員対象に、川勝教育長から「教職員として大切にしてほしいこと」と題して講義がありました。教育長のこれまでの経験を踏まえながら、教科指導・各領域に渡ってお話がありました。これからの実践に向けてポイントをしぼって改めて学ぶ機会となりました。

スキルアップ講座4<11月28日実施>
5回シリーズの4回目。事前の課題「語り」と「記述」のリフレクションについて小グループで意見交流後、一つの事例をもとにグループ省察を行いました。振り返りの重要性の中で、参加者自身が「書く」ことや「聞く」ことの体験を通して今後の実践につながる学びの機会となりました。

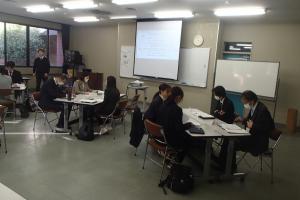
子どもの発達専門講座Ⅱ<11月14日実施>
今回も通級指導教室の先生方との交流の中で実際の検査から発達の様子について学ぶことができました。目の前の子どもたちのよりよい将来を見据えて、支援・指導の工夫に役立てる機会となりました。


道徳教育講座<11月13日実施>
昨年度に引き続き、講師として四天王寺大学の杉中康平教授にお越しいただきました。今回はテーマを評価に絞って進めていただき、講師の先生からのさまざまな問いをもとに、参加者はグループ対話を通して考えをまとめ上げながら学びにつなげていきました。



人権教育(LGBTQ+)講座<11月10日実施>
講師の先生ご自身のライフストーリーをもとに当事者としての思いを理解する機会になりました。また、「安心して過ごせる学校にするために」さまざまなケースがある中で正しい理解や情報発信について学びました。後半は、いろいろな事例をもとに実際の対応に関わって、グループワークの中で考えを出し合いました。


子どもの発達専門講座Ⅰ<10月28日実施>
発達検査を確認しながら支援のあり方を学ぶということで、発達のすじみちについて年齢を追って順に確認しました。また、目に見えない世界を想像して紙の上で学ぶ力など、実際にワークを通して発達について深く考える機会となりました。



亀岡の学力向上講座Ⅱ
(第2回学力担当者会議) <10月27日実施>
関西大学文学部 岩﨑保之教授をお招きし、亀岡市の令和7年度全国学力・学習状況調査の分析結果の報告と、グループ別ワークショップを行いました。グループ別ワークショップでは、岩﨑教授にファシリテートをお世話になり、学力向上における共通課題を整理した後、かめ学サイクル(学習サイクル)と結びつけた課題の解決策について熱心に協議が展開されました。最後に、岩﨑教授から子どもは「強みから伸びる」ことや「非認知能力の向上が認知能力の向上に繋がる」ことなどについて指導助言をいただきました。


亀岡のICT教育推進講座Ⅱ<10月21日実施>
全国学力学習状況調査の質問調査の状況から分析結果を確認し、情報活用能力に関わって現行の学習指導要領や中教審の論点整理にも触れ、市内の状況を確認しました。その後グループ協議の中で、「GIGAワークブックかめおか」を使う体験や、各校の情報教育の現状・充実について交流を深めました。


人権教育(同和教育)講座Ⅱ<10月7日実施>
ガレリアかめおかで、社会教育課との共催で人権教育指導者研修会参加しました。いろいろな差別の例を交えながら人権課題に共通するところなどをお話しいただきました。後半は、アンコンシャスバイアスやマイクロアグレッションなどについても触れていただきました。

スキルアップ講座Ⅲ<10月6日実施>
5回シリーズの3回目。小グループで、あるシチュエーションをもとに児童生徒への関りについてロールプレイングを行いました。自身の指導の在り方を振り返るとともに、その時その時の子どもたちの気持ちに身を置くこともできました。


教育セミナー<8月20日実施>
今年度は、中学校ブロックの小中合同研修会の場で5会場に分かれてオンラインによる開催となりました。講師として、熊本大学大学院 特任教授の前田康裕先生に「子どもと教師の学び方改革」と題して講演をお世話になりました。対話やICTの活用など授業改善や、主体的な学びや振り返りなど幅広く取り上げていただき、また、教師の学びについても考える機会となりました。途中、校種をまたいだグループでの参加者同士の対話を交えながら学びを深めることができました。




スキルアップ講座Ⅱ<8月1日実施>
5回シリーズの2回目。「特別支援教育の視点を生かした学級経営」では、言葉の下や行動の背景に目を向けることなどをもとに、みんなにやさしい学級づくりを意識しました。後半は、「生徒指導の在り方について」では知識と対応の関係をもとに子どもの変化に気づく初期対応について学びました。


幼児教育講座Ⅰ<7月30日実施・オンライン>
一般社団法人誠智愛の会 Minds & Hopes 所長 服巻 智子様に佐賀県からオンラインで講座をお世話になりました。今回は、市内の保育所・こども園・幼稚園・小学校・義務教育学校の先生方が参加をし、自閉スペクトラム症を中心に専門的な知識をはじめ、実践的な部分を交えながらお話しいただきました。「人は必ず成長する。」人の成長を信じながら、幼児期から学校へ通う時期のそれぞれのステージで子どもたちに関わる先生方やその子の背景、そして社会のあり方などを考える機会となりました。

創造的な授業づくり講座Ⅱ<7月4日実施>
府エバンジェリスト育成研修受講者の実践発表として2名の先生から、創造的な授業について大切にしてきたことや、社会とのつながりや探究的な学びについてなどの発表がありました。後半は、参加者同士で実践の交流を行いました。

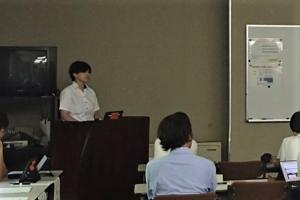

ICT教育管理職対象講座
<6月30日実施・オンライン>
鹿児島国際大学 准教授 辻 慎一郎先生に講師をお世話になりました。目の前の子どもたちの未来をイメージしながら教育改革の必要性をわかりやすく説明していただき、現行の学習指導要領が求めていることや現場での課題となることを交えて、学校Dxについてポイントを押さえながら進めていただきました。


特別支援教育講座<6月27日実施>
花ノ木医療発達支援センター長の鋒山先生を講師として、「通常の学級での特別でない支援について」ご講義をお世話になりました。「明日から使える」という言葉で始まり、歴史的な背景を交えてさまざまなケースについて具体的にそして専門的に詳しくお話をしていただきました。

副校長・教頭講座<6月19日実施>
南丹教育委員会連絡協議会との共催で、管内教頭会議とあわせた開催でした。南丹教育局長をはじめ、南丹局からそれぞれの担当の立場で管内の現状、服務管理、学校運営、危機管理などについて詳しく講義がありました。参加者がアップデートできる機会となりました。



教育相談講座<6月17日実施>
前半は、社会福祉という立場で、家族との向き合い方や学校での困りごとに対する向き合い方を考えました。また、対話を通してわかることやクリティカルシンキングなどの思考スキルを意識する機会にもなりました。後半は時間を多くとり、グループで普段の実践からお互いの話を聞くことを意識しながら交流を深め合いました。


亀岡の学力向上講座Ⅰ
(第1回学力担当者会議)<6月16日実施>
「亀岡市確かな学力育成ビジョン」に基づく亀岡の学力向上の取組の一環として、各校の学力担当者の参加による「亀岡の学力向上講座Ⅰ(第1回学力担当者会議)」を開催しました。
今回は、子どもたちが主体的に学習に取組む習慣を身に付けさせるための学習サイクルをテーマに研修を行いました。
最初に亀岡市が進めている学習サイクル「かめ学サイクル」の趣旨説明と実践協力校(曽我部小・薭田野小・保津小)の取組を紹介し、主体的な学習習慣の定着のための実践について学びました。
続いてグループに分かれ、各校での学習サイクル定着の工夫や中学校ブロックでの連携の取組など交流、協議を行いました。
最後に関西大学文学部教授の岩﨑保之先生から、「主体的に学習する力をどう育成するか」と題して、AARサイクルや「主体的な学び」を具現するための教師の支援の在り方などについて、ご講義並びに指導助言をいただきました。


スキルアップ講座Ⅰ<6月9日実施>
5回シリーズの1回目。「講座参加者に期待すること」では、京都府教員などの資質能力向上に関する指標をもとに、初任期の教員に求められることをはじめ、ポイントを絞って講義があり、改めて日常の実践について振り返る機会となりました。後半は、学級経営になぜ人権教育かを確認しつつ、人権教育の視点に立った学級経営について対話や心理的安全性などに触れながら研修を深めました。


情報モラル教育講座<6月5日実施・オンライン>
一般社団法人メディア教育研究室 代表 今度珠美様に講師としてお世話になり実施しました。メディアバランスについて、SNSとのつきあいかた、デジタルシティズンシップについて、それぞれポイントとなるところを押さえて講義がありました。後半は、ネットいじめの教材について、グループで意見交流を行いました。

教師のためのかめおか学講座<6月3日実施>
亀岡市文化資料館を会場として副館長様から新転任の教職員を対象に講義がありました。その昔、亀岡を訪れたであろう歴史上の人物や建物、また、地名との関係など身近なところで詳しく説明がありました。教科書には載せられていない亀岡の話など、授業でのネタにできそうなことにも興味をもてました。後半は、常設展の展示を見学しました。


創造的な授業づくり講座Ⅰ
<5月27日実施・オンライン>
確かな学力育成ビジョン」にも掲げる「探究的な学び」の具体的な実現に向けて、授業改善に取り組む力を高めることを目的とし、教職経験概ね15年目以内の先生方を対象とした4回シリーズの1回目。変化の激しいこれからの時代に向けて育むべき資質能力を整理し、創造的な授業についてイメージをもちました。また、多様なアウトプットについて考える機会にもなりました。

人権教育(同和教育)講座Ⅰ
<5月22日実施・オンライン>
同和問題を中心とする人権教育について、教職経験概ね15年目以内の先生方を対象とした3回シリーズの1回目。歴史的な経過や現在の状況について確認し、人権教育に携わる立場として、人権に向き合い、どのように人権教育・人権学習を進めていくかということ、そして、同和教育の意義について考えていきました。

安全教育講座<5月20日実施>
自治防災課長から、交通事故の発生状況や昨年の道路交通法の改正による罰則規定強化などをもとに、自転車などの交通事故防止について確認をしました。災害発生時の学校の対応について、市内の避難所についても説明がありました。また、学校教育課指導主事からは、震災で大きな被害にあわれた地域での研修をもとに、災害発生時の教職員の役割や避難訓練の在り方などについて参加者が考える機会となりました。


亀岡のICT教育推進講座Ⅰ<5月12日実施>
前半は、ICT推進委員の役割の確認として、端末・アカウントの管理や支援員さんとの関りなど。後半は、デジタル教科書の利用についてなど担当指導主事から講義がありました。また、支援員さんにお世話になっていることや端末の持ち帰りなどについて、参加者同士の対話を通して各校の状況交流を行いました。最後に本年度の重点目標を確認しました。



特別支援教育コーディネーター講座
<4月18日実施>
特別支援教育コーディネーター・通級指導担当の先生を対象に、その役割、確認事項の説明や講義がありました。ソーシャルスキルトレーニングについては、世の中の変化を交えながら3つの柱と基本スキルをもとに、Sstのねらいなどを学びました。また、教育相談についてその目的やその流れを確認しました。後半は、各中学校ブロックで情報共有や課題解決に向けての協議などを行いました。