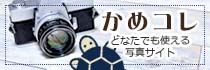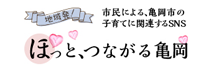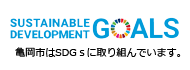本文
国保で受けられる給付
療養の給付
病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示すれば医療にかかった費用の一部を支払うだけで、医療を受けることができます。残りは国保が負担します。
70歳未満の人
|
区分 |
負担割合 |
|---|---|
|
義務教育就学前まで |
2割 |
|
義務教育就学後 |
3割 |
70歳から74歳までの人
(後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害があると認定された人は除く)
高齢受給者証について
70歳以上の方は75歳になるまでの間、「高齢受給者証」が交付されます。
対象となるのは、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
医療機関受診の際は、国民健康保険被保険証と「高齢受給者証」を一緒に提示してください。
|
区分 |
負担割合 |
|---|---|
|
一般 |
2割 |
|
現役並み所得者(※) |
3割 |
(※)現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の人と、その同一世帯の人です。ただし、平成27年1月以降新たに70歳となる国保被保険者のいる世帯のうち、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の世帯に属する人は「一般」の区分と同様になります。
*高齢受給者証は毎年8月に更新を行います。ただし、世帯に異動などがあった場合は、その都度負担割合の再判定を行います。

入院時食事療養費の支給
入院中1食の食事にかかる費用のうち、一部(標準負担額)を被保険者に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
| 所得区分 |
食事代(1食) 令和7年3月まで |
食事代(1食) 令和7年4月から |
|
|---|---|---|---|
|
住民税課税世帯 |
490円 |
510円 | |
|
住民税非課税世帯 |
過去12カ月の入院日数が90日まで |
230円 |
240円 |
|
過去12カ月の入院日数が90日を越える |
180円 |
190円 | |
| 低所得者1 |
110円 |
110円 | |
※低所得者2…住民税非課税世帯に属し、低所得者1に該当しない70歳以上75歳未満の人
※低所得者1…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ、各種所得などから必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる70歳以上75歳未満の人
住民税非課税の人、低所得者1または2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です(マイナ保険証を利用する場合、提示は不要です)。詳しくは「限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の申請・更新について」をご確認ください。
療養費の支給
次の場合で医療費の全額を支払ったとき、申請によって、義務教育就学前の人は8割、義務教育就学後70歳未満の人は7割、70歳以上の人は8割(現役並み所得者は7割)分の相当額を国保から支給します。
- 急病などでやむを得ず、マイナ保険証もしくは国民健康保険証または資格確認書を提示しないで診療を受けたとき
- 骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師の指示で、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき
- コルセット(医師が認めたとき)などの補装具代、輸血のための生血代
- 海外渡航中に医療を受けたとき(診療内容明細書、領収明細書に日本語の翻訳文の添付が必要)
※海外渡航中に医療を受けたときは、「国民健康保険の海外療養費制度」を参照してください。
そのほかの給付
|
出産育児 |
被保険者が出産したとき出産育児一時金として50万円(※1)または48万8千円(※2)を支給します。 |
|---|---|
|
葬祭費 |
被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った人に対して、5万円を支給します |
交通事故にあったとき
交通事故など、第三者の行為でけがをしたときの医療費は加害者が本来負担すべきものですが、加害者と話し合いがつかないような場合には、国保で診療を受けることは差し支えありません。しかし、国保で診療を受けた場合の医療費は国保が一時的に立て替えているに過ぎず、後で加害者に請求しなくてはなりません。必ず国保に届け出をしてください。
示談の前に必ず届け出を!
示談をしてしまうと国保が使えない場合があります。
交通事故にあったら
- 警察に届ける。
- 必要書類を国保の窓口へ提出する。(詳しくはこちら[Wordファイル/31KB]をご覧ください。)