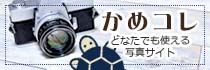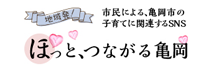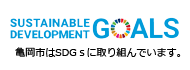本文
こども医療費助成制度
こども医療費助成制度は、健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、お子さんが元気で丈夫に育つことを願って保護者が支払う医療費を亀岡市が助成するものです。
こども医療費助成制度とは
亀岡市にお住まいで、公的医療保険に加入しているお子さんが対象(詳しい対象者は、「対象者」の欄をご参照ください)となり、入院・通院にかかる医療費(公的医療保険の自己負担額)を亀岡市が助成します。
※保護者などの所得制限はありません。
こども医療の助成対象
保険診療が行われた場合の公的医療保険の自己負担額が助成の対象となります。保険診療の対象とならない次のものなどは、こども医療費助成の対象になりません。
- 予防注射、健康診断の費用、薬の容器代、文書料
- 入院時の食費負担額、差額ベッド代
- 200床以上の病院での初診時の特別料金など
対象者
次の項目のすべてに該当する子どもに助成します。
- 市内に住所を有している子ども
- 公的医療保険などの被保険者、または被扶養者となっている子ども
- 出生日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(※高等学校に通っていない人も対象です。)
※生活保護、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療など他の制度対象となる場合は、こども医療費の対象になりません。
受給者証の交付の手続
健康保険証(お子さんの名前が記載されているもの)をお持ちのうえ、子育て支援課で申請をしてください。
認定された人には「こども医療費受給者証」を交付します。
※出生により申請される人は、先に公的医療保険への加入の手続を済ませてください。
一部負担金について
<令和5年9月診療分から> ( )内はこども医療費受給者証の色
|
|
0歳~18歳 (出生日から18歳に達する日以後最初の3月31日まで) |
||
|---|---|---|---|
|
入院 入院外 (通院) |
無料 (淡い水色) |
||
医療機関を受診するとき(受給者証の使い方)
「こども医療費受給者証」を「健康保険証」と一緒に、医療機関の窓口に提示してください。
※京都府外では、入院・通院ともに、医療機関の窓口で受給者証は使用できません。一旦自己負担額をお支払いいただいた後、申請により、口座振込の方法で助成(償還払い)します。(詳しい内容は、『医療機関の窓口でこども医療費の助成が受けられなかったとき』をご参照ください)
医療機関の窓口でこども医療費の助成が受けられなかったとき
京都府外の医療機関を受診した場合など、医療機関の窓口で、こども医療費の助成が受けられなかったときは、以下「申請に必要なもの」をお持ちいただき、子育て支援課で、こども医療費助成の申請をしてください。後日、口座振込の方法で助成(償還払い)します。
申請に必要なもの
1.「こども医療費受給者証」および「健康保険証」(お子さんの名前が記載されているもの)
2.医療費を支払ったことを証明する書類の原本(保険点数の記載されている領収書)
※レシートの場合は、医療機関で保険点数および受診者名の記載を受けてください。
※お預かりした領収書原本は返却できません。領収書原本の返却を希望される人はあらかじめコピーを取っていただいたうえで、原本とコピーを一緒にお持ちください。(原本は、受付印を押して返却します)
3.申請者名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
※申請の際は診療月が過ぎてから申請してください。(同一診療月分はまとめて申請をお願いします。)
(例)令和5年9月診療分は、令和5年10月以降に申請してください。
※上記1.~3.は、申請時に確認します。毎回必ずお持ちください。
- こども医療費助成の申請は、医療機関受診日から5年で時効となります。
届出のお願い
次のような場合は、すみやかに子育て支援課に届け出てください。
- 加入している公的医療保険に変更があったとき
- 住所や氏名に変更があったとき
- 受給者証を紛失・破損したとき
こども医療を受けられなくなるとき
次の場合には、こども医療の受給資格がなくなり、受給者証が使えなくなりますので、子育て支援課に受給者証をご返却ください。
- 受給者証の有効期限に達したとき(有効期限は受給者証の上部に記載されています)
- 亀岡市外へ転出するとき
- 公的医療保険の資格がなくなったとき
- 生活保護、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療など、他の制度により医療費の給付を受けるとき
その他
- 健康保険証を医療機関に提示せず受診し、医療費を全額自己負担した時や、治療用装具(コルセットなど)を装着した時は、加入している公的医療保険へ療養費の請求を行った後、子育て支援課でこども医療費助成の申請をしてください。
申請をするには、『医療機関の窓口でこども医療費の助成が受けられなかったとき』に記載の「申請に必要なもの」のほか、公的医療保険の療養費支給決定通知書が必要です。
また、治療用装具(コルセットなど)にかかる申請には、装具装着証明書、医師の意見書、装具の領収書、装具の仕様書もあわせて必要になります。 - 公的医療保険の自己負担額が高額療養費に該当するときは、加入している公的医療保険へ高額療養費の請求を行った後、子育て支援課でこども医療費助成の申請をしてください。
申請をするには、『医療機関の窓口でこども医療費の助成が受けられなかったとき』に記載の「申請に必要なもの」ほか、公的医療保険から交付される高額療養費支給決定通知書が必要です。 - 学校や保育所などでの負傷や疾病により、医療機関で治療を受けた場合の医療費については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるため、こども医療費助成制度による医療費助成ではなく、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度をご利用ください。
様式集
- こども医療費受給者証交付(再交付)申請書 [PDFファイル/73KB]
- こども医療費受給異動届出書 [PDFファイル/64KB]
- こども医療費助成申請書 [PDFファイル/128KB]
- (記入例)こども医療費助成申請書 [PDFファイル/156KB]
こども医療費助成制度を拡充しました(令和5年9月診療分から)
- 令和5年9月1日以降の診療分から、18歳(18歳に達する日以後最初の3月31日)までのお子さんが無料で保険診療が受けられるよう、こども医療費助成制度を拡充します。医療機関の窓口で健康保険証と、こども医療費の受給者証を提示することで、無料で保険診療が受けられます。
詳しくは「こども医療費助成制度を拡充します」をご確認ください。