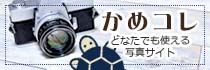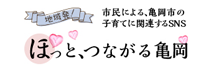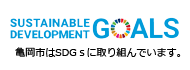本文
亀岡市国民健康保険料の減額制度
国民健康保険料の法定軽減について(申請不要)
世帯全員が所得の申告をしていて、前年の世帯の所得合計(擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得を含む)が、国の定める所得基準以下である世帯については、国民健康保険料の均等割額と平等割額を下表の割合で減額します(毎年度4月1日現在の加入者数をもとに判定します)。
税制改正に伴い、令和7年度から減額割合ごとの所得要件が変更となっています。
| 減額対象項目 | 減額割合 | 対象世帯の所得要件 |
|---|---|---|
| 均等割額と平等割額 | 7割軽減 | 前年の世帯の所得合計≦430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1) |
| 5割軽減 |
前年の世帯の所得合計≦430,000円+(305,000円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)+100,000円×(給与所得者等の数-1) |
|
| 2割軽減 | 前年の世帯の所得合計≦430,000円+(560,000円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数))+100,000円×(給与所得者等の数-1) |
前年中所得が一定額以下の世帯の負担軽減を目的として均等割・平等割額の5割軽減および2割軽減判定の際の軽減判定基準額が引き上げられました。
軽減判定所得が下記の基準以下の場合に均等割・平等割額がそれぞれの割合で軽減されます。
税制改正についての詳細は、「令和7年度から適用される税制改正について」をご参照ください。
※1 軽減判定の際の「所得」は、次の点が所得割算定の際の基準総所得額(基礎控除後の総所得金額など)と異なります。
- 基礎控除額(43万円)を差し引く前の所得で判定します。
- 擬制世帯主の所得も判定に含まれます。
- 事業収入の場合、青色専従者および事業専従者控除は必要経費に含まれません。
- 給与収入の場合、専従者給与額は含まれません。
- 公的年金収入の場合、令和6年度は昭和35年1月1日以前生まれの方について、公的年金など控除額後の所得から、さらに15万円を控除します。
- 土地・建物などの譲渡所得は、譲渡所得にかかる特別控除を差し引く前の金額となります。
- 雑損失の繰越控除については軽減判定においてのみ適用されます。
※2「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)および一定の公的年金などの支給を受ける方(公的年金などの収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金などの収入が125万円を超える65歳以上の方)です。
※3「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険を脱退した方のうち、同じ世帯に国民健康保険被保険者がいる方です。ただし、継続して移行時と同じ世帯であることが条件となります。
未就学児にかかる国民健康保険料の均等割額の軽減について(申請不要)
子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、未就学児にかかる均等割額の軽減措置を行っています。
対象となる被保険者
- 未就学児(6歳に達する日以後、最初の3月31日以前である被保険者)
- ※令和7年度分については、平成31年4月2日以降に生まれた方が対象になります。
-
軽減の内容
-
国民健康保険加入者の医療分・支援金分のうち、未就学児にかかる1人あたりの均等割額が5割軽減されます。
-
後期高齢者医療制度移行に伴う国民健康保険料の軽減特例措置(申請不要)
国民健康保険被保険者が75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行され、国民健康保険被保険者が1人になった場合、医療分・支援金分の平等割を最大5年間2分の1に減額します(特定世帯)。
また、特定世帯期間満了後の世帯は医療分・支援金分の平等割を最大3年間4分の3に減額します(特定継続世帯)。
※期間中に世帯構成などの異動があった場合は、必ずしも継続される制度ではありません。
産前産後期間の国民健康保険料が免除されます(申請必要)
国民健康保険に加入している方が出産予定又は出産された場合に保険料を免除します(令和6年1月から)。
国民健康保険加入者で出産予定の方(出産された方)がいる世帯は、出産者の出産予定月(または出産月)の前月から4ケ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ケ月前から6ケ月間)相当分の所得割・均等割保険料が年額から減額されます。
【参照】産前産後保険料免除リーフレット [PDFファイル/439KB]
対象となる被保険者
・令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険加入者の方
・妊娠85日(4ケ月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。
申請の受付期間
・出産予定日の6ケ月前から届け出ができます。出産後の届け出も可能です。
届出方法および届出書ダウンロード
申請方法:郵送または保険医療課窓口(1階7番窓口)に提出
申請は郵送による手続きも可能です。各種申請に必要な以下の書類をダウンロードし、添付書類をつけて以下「お問い合わせ」あてに郵送してください。必要書類がダウンロードできない場合は、市役所より郵送させていただきますので、以下「お問い合わせ」あてにご連絡ください。
ア:産前産後期間に係る保険料軽減届出書 [PDFファイル/126KB]
イ:母子健康手帳[表紙および出産予定日(出産日)が記入されている部分]※郵送の場合はコピー
ウ:届出人の本人確認書類(顔写真付きのもの1点もしくは、顔写真付きでないもの2点)※郵送の場合はコピー
エ:別世帯の方が届け出る場合は委任状が必要です。
非自発的理由で失業された方は国民健康保険料などが軽減されます(要申請)
会社の倒産や解雇など事業主の都合や、雇用期間満了などのやむを得ない理由で離職した65歳未満の方(非自発的失業者)は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算し、国民健康保険料を軽減することができます。また、高額療養費などの給付基準も変更になる場合があります。該当する方は届け出てください。
対象となる被保険者(特例対象被保険者など)
次の要件に当てはまる場合に対象となります。
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給者資格通知(ハローワーク発行)をお持ちで、離職日時点で65歳未満の方のうち、証に記載されている離職理由の番号が、11、12、21、22、23、31、32、33、34の方(※「特例受給資格者証」をお持ちの方は、軽減対象者には該当しません。また、雇用保険の手続きを行っていない方の申請も受付できません。)
対象となる期間(国民健康保険料)
|
離職年月日 |
国民健康保険料軽減対象期間 |
|---|---|
|
令和6年3月31日~令和7年3月30日 |
離職した日の翌日の属する月~令和8年3月末 |
|
令和7年3月31日~令和8年3月30日 |
離職した日の翌日の属する月~令和9年3月末 |
※高額療養費などの軽減対象期間は国民健康保険料と異なり、令和5年3月31日から令和6年3月30日までに離職した方も、令和7年7月末まで対象となります。
※軽減期間中に社会保険などに加入し、国民健康保険の資格を喪失した時点で軽減措置は終了します。
申請方法および申請書ダウンロード
申請方法:郵送または保険医療課窓口(1階7番窓口)に提出
申請は郵送による手続きも可能です。各種申請に必要な以下の書類をダウンロードし、添付書類をつけて以下「お問い合わせ」あてに郵送してください。必要書類がダウンロードできない場合は、市役所より郵送させていただきますので、以下「お問い合わせ」あてにご連絡ください。
ア:非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減の届出書(PDF:80KB)
記入例:非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減の届出書(PDF:171KB)
イ:雇用保険受給資格者証のコピー[両面]
ウ:届出人の本人確認書類(顔写真付きのもの1点もしくは、顔写真付きでないもの2点)※郵送の場合はコピー
災害等の減免について
不慮の災害などにより重大な損害を受けたとき、予期せぬ失業などにより前年と比較して収入が著しく減少したときなど、その他特別な事情により生活が困窮し、国民健康保険料の納付が困難であると認められる場合は、国民健康保険料を減免できる場合があります。詳しくは、保険医療課へ問い合わせてください。