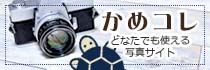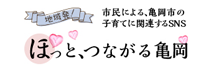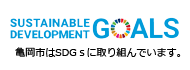本文
国民年金保険料の免除制度
保険料免除制度
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定基準以下であれば、保険料の全額または一部の免除を受けることができる制度です。
申請が遅れると申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますのでご注意ください。
対象者
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な方で、所得の基準を満たす方
所得の基準
本人・配偶者・世帯主の前年所得(1~6月は前々年)が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
- 全額免除の基準 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
- 4分の3の基準 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+88万円
- 半額の基準 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+128万円
- 4分の1の基準 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+168万円
※地方税法で定める障害者・寡婦またはひとり親である場合は、前年所得が135万円以下
承認期間
7月から翌年6月まで
- 原則として、毎年度(7月以降)申請が必要です。申請が遅れると万が一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、毎年7月以降速やかに申請をお願いします。なお、過去の期間は申請日から2年1カ月までさかのぼって申請することができます。
- 全額免除を承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度以降は、改めて申請を行わなくても、継続して全額免除の申請があったものとして審査を行います。
※災害・失業等による承認を受ける場合には、継続申請はできません。改めて申請が必要となります。
| 免除区分 | 免除後の保険料(令和7年度分) |
|---|---|
| 全額免除 | なし |
| 4分の3免除 | 4,380円 |
| 半額免除 | 8,760円 |
| 4分の1免除 | 13,130円 |
納付猶予制度
所得の高い世帯主と同居していても、本人と配偶者の所得が一定額以下であれば、保険料の納付を先送り(猶予)にできる制度です。
対象者
所得の基準
本人・配偶者の前年所得(1~6月は前々年)が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
- 納付猶予の基準 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
承認期間
7月から翌年6月まで ※年度の途中で50歳になる場合は、50歳になる前月まで
- 原則として、毎年度(7月以降)申請が必要です。申請が遅れると万が一の際に、障害年金などを受け取れない場合がありますので、毎年7月以降速やかに申請をお願いします。なお、過去の期間は申請日から2年1カ月さかのぼって申請することができます。
- 納付猶予を承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度以降は、改めて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして審査を行います。
※災害・失業などによる承認を受ける場合には、継続申請はできません。改めて申請が必要となります。
学生の方は、本人の所得が一定基準以下の場合、在学期間中の保険料の納付を先送り(猶予)にできる「学生納付特例制度」が申請できます。詳細は以下のページをご覧ください。
国民年金保険料学生納付特例制度をご存じですか(別ウインドウで開きます)
失業等による特例認定
対象年度の所得が免除・納付猶予の基準を超えていても、失業等により保険料の納付が困難な場合は、特例認定を受けることができます。
申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(失業等)された場合、退職(失業等)された方の前年の所得をゼロとして審査します。
特例認定に必要な書類
失業による特例認定を受けるために必要な添付書類は下記のうちいずれか1点です。審査対象者の中に失業による特例認定の対象となる方が複数人いる場合は、対象者全員分の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
- 公務員だった人は退職辞令 など
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除・納付猶予の臨時特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例を利用した国民年金保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)の申請が可能です。申請は令和4年度分まで可能です。詳細は以下のページをご覧ください。
法定免除制度
次のいずれかに該当した場合は、届け出によりその間の国民年金保険料が免除されます。
〇 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
〇 生活保護の生活扶助を受けている方
〇 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
追納制度
免除・納付猶予の承認を受けた期間は、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。老齢基礎年金の年金額を計算するときに、免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。追納をすることで老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は加算額がつきます。
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度<外部リンク>