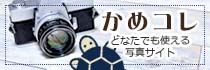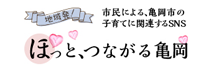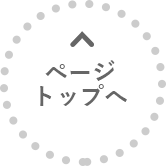本文
SDGsの取組み最前線! 亀岡市の事業者紹介(株式会社もり)
「食品廃棄物をゼロに近づけ、亀岡の自然を大切にする」自社農場を運営する株式会社もりの取組み

本インタビューは、より身近なSDGsの事例を知っていただくために、亀岡市内でSDGsを積極的に推進する事業者の実践事例を紹介します。
食品製造業から排出される「食品残さ」(しょくひんざんさ/食品廃棄物)の処理は頭が痛い問題です。農林水産省の調査によると、食品製造業が年間に排出する食品残さの量は1,315万tに及びます(令和4年度※1)。食べ残しが問題になる外食産業ですら99万tですから、その量がいかに甚大であるかが、おわかりいただけるでしょう。
そのような製造中に出てしまうごみをどのように活用し、持続可能な経営に結びつけるかを考えているのが、京つけもので知られる「株式会社 もり」です。

同社は漬物製造の過程で発生する生ごみを堆肥化・飼料化するなど環境を考慮したさまざまな方法で有効利用し、人々の暮らしに還元・循環させています。
「環境について考えて取り組んだ結果、当社から生ごみの廃棄はほぼなくなりました」。そう語るのは代表取締役の森義治さんです。どのような対策を経て生ごみゼロに近い成果をあげられたのでしょう。また、SDGsを社是に採り入れたことで、どのような意識の変革があったのでしょう。
代表取締役の森義治さん、製造部次長の宮木健一さん、お二人にお話を伺いました。

左)代表取締役の森義治さん、右)製造部次長の宮木健一さん
自分たちで野菜を栽培して感じた亀岡の魅力
株式会社もりは1962年創業の漬物メーカーです。亀岡市篠町の「亀岡漬処」やJR京都駅構内をはじめ、府下に13の直営店を構えています。
同社は亀岡の曽我部町・千歳町の2町3か所に計およそ2ヘクタールに及ぶ自社農場を擁しているのが特徴で、モットーは「土が原点」。環境にやさしい緑肥を採用しながら3年もかけて栽培に適した土壌をつくり、聖護院かぶらや鹿ヶ谷かぼちゃなど、さまざまな旬の京野菜を自社で育てているのです。特に青味大根は絶滅の危機に瀕していた品種で、もりの尽力で蘇らせた功績があります。

亀岡と西院・太秦の3か所に製造工場があり、「千枚漬」「すぐき」など京漬物の伝統を守り続ける、もり。反面、トレンドにのっとりトマトやオリーブの漬物・ピクルスなど洋風の発酵食品の味にも定評があり、食卓をいっそう楽しいものにしてくれます。
自ら額に汗して畑を耕している森さんは、もりの2代目です。2001年に後を継ぎました。
森義治さん(以降、森):もともとは先代である父・春生が、お寿司屋さんで使うガリを漬けて売り始めたのが起業のきっかけです。
創業当時は商品を新聞紙で包んで売っていたのですが、時代の進化とともに真空パックが可能になりましてね。1975年に開業した東映太秦映画村のおみやげとして販売し始めたことで会社が成長して参りました。
漬物の需要が高まり、素材を育てる畑と工場拡大の必要に迫られ、平成元年(1989)、かぶらの産地である亀岡に自社農園を拓きました。同時に、亀岡の農家の組合にも加入したのです。

亀岡に自社農場を設け、漬物メーカーであるとともに生産者になった森さんたち。亀岡で野菜を育てる経験を通じて、改めて亀岡の魅力に気がついたと言います。
森:亀岡は霧が深く、空気中の水分が野菜をみずみずしくしてくれるのです。当社では「朝霧千枚」といって、亀岡の霧を活かしながら聖護院かぶらの栽培をしています。お客様から予約を取りつけ、「よく育っています」「今日、収穫しました」と、かぶらの育成状況を報告しながら販売する。当社にはそんな特別な千枚漬けもあるんです。亀岡で栽培しているからこそ実現できた商品ですね。
自ら畑へ出て農作業にいそしみ、野菜の生育状態を見極める森さん。ときには会社にいても、畑にいる社員から「社長、雑草が生えてますよ」と呼び出しがかかる場合もあるのだそうです。

孫ができて気がついたSDGsの大切さ
京の食文化を今に伝え、一般ユーザー向けに予約制のぬか漬教室も開催している、もり。そのようななか、森さんがSDGsを意識しはじめたのは「ここ4年ほどだ」と言います。
森:はじめは「SDGs? なんやそれ」という感覚でした。しかし学生さんたちが学校でSDGsを真剣に学んでいる姿を見て、『近い将来きっと、会社がSDGsに取り組んでいる姿勢が商品の購買動機につながったり、就職先の選択肢の一つとして、とても重要な要素になったりするだろう』と感じました。
それに、自分自身に孫ができたのが、大きなきっかけかな。この子の未来のために、なにかせなあかんなと思いましたね。私たちの年代が後世に何を残せるのか、それを真剣に考えないといけない時期にきていると考えています。
勢いよくSDGsの旗を揚げた森さん。製造部次長の宮木さんは当時の様子をこう振り返ります。
宮木健一さん(以降、宮木):また何か始まったぞ、という感じでしたね。社長は社内の誰よりも感覚が若いので、時流にとても敏感なんです。ついていくのが精一杯ですが、年長者が次世代のために率先して動いてくれるので頼もしいと感じています。

そうして、もりの重点的な取り組みの一つとなったSDGs。しかし、唐突にSDGsに取り組むといっても、まず何をすべきなのかがわからない。悩んだ森さんはスタッフとともに、すでに会社が実行している仕業を列挙し、SDGs17項目に該当する事柄をさらに強化する策を執ったのです。
森:現在もりがやっているプロジェクトをとにかく全部、洗いだしてみたんです。するとね、当社もすでにけっこうSDGsにつながることをやってたんですよ。『なんや、もうやってるやん』って。だったら、それら事例に肉付けをしてSDGsを推進していこう、そんな流れになりました。
「食品残さ」の問題を堆肥化・飼料化で解決
もりをはじめ食品メーカーにとって大きな課題は産業廃棄物「食品残さ」の処理です。食肉の骨、魚介の殻など食品素材から発生する生ごみは水分を多量に含んで非常に重く、焼却の際には多くのエネルギーを必要とします。また、燃焼に時間がかかり、CO2の排出量も増え、環境によくないとされています。
もりもまた、漬物づくりの工程で除去された野菜の葉や、いわゆる「へた」と呼ばれる野菜くずが出ます。そこで対策したのが堆肥化と飼料化です。もりでは野菜くずの一部を「エコの森京都 京都有機質資源株式会社」を通じて肥料・飼料へと再生化し、地球へと還元しています。
また、野菜の端材を新鮮なうちに他の漬物メーカーと共同で京都市動物園へ寄付し、動物たちのエサにする活動も行っています。それは食品ロスを解消するのみならず、動物園の運営費の支援にもつながっているのです。
森:動物園だけではなく、リクガメを飼っている喫茶店にも週に1度、大根の葉っぱを寄付しているんです。もう7年になるのかな。「エサ代がかからない」と喜ばれているんですよ
もう一つ、食品残さの処理方法として新たに導入したのが、バクテリアによる分解です。バクテリアがなんと一夜にして生ごみを食べてしまい、翌日には液状化しているというから驚かされます。そうして排水基準内に収まった液体を下水として流すのです。
この方法だとごみを他所へ運搬しないため自動車輸送にかかる燃料費を抑えられ、排気ガスも出ません。この方法で1日300キロの食品残さを処理できるようになったのだとか。

本社工場裏に設置された専用の機械により分解中の食品残さ
森:主にこの3つの方法で、当社からはごみが出なくなりました。段ボールなども再生紙にしていますので、何も出ないんです。
こうして廃棄物の削減に大きな成果をあげた、もり。しかし、言い方を変えれば、社内での作業が増えたとも言えます。スタッフは現状をどのように捉えているのでしょう。
宮木:はじめは正直、「手間だな。面倒だな」と感じました。しかし馴れてきたら、なんともない。現在はむしろ当たり前という感覚です。SDGsは行動に落とし込むことで日常化するのだなと思いました。
森:幸か不幸か、うちはまだ創業63年。老舗じゃないから、しがらみもなく、フットワークを軽くしながら動ける部分はあると思いますね。
障がい者の就労支援などSDGsに多角的に取り組む
食品残さ対応のみならず、もりはSDGsに対して多方面に挑んでいます。障がい者の就労支援も、その一つ。京都市内にある就労継続支援B型事業所「五力工房(ごりきこうぼう)」と提携し、障がい当事者の施設外就労の場の一つとして、年間に6回ほど自社農場での野菜の収穫など仕事を促しています。
森:京都市内にある施設では日頃パンを焼いておられ、当社とコラボした漬物パンを特別につくってもらうこともあります。親御さんからは「我が子が他業種のお手伝いができた」とお喜びいただいています。

もう一つは、太陽光発電です。もりでは再生可能エネルギーを有効活用するために、本社三条店の屋上と亀岡工場に太陽光発電パネルを設置しています。発生した電気は、本社ならびに亀岡工場の一部で実際に使用しているのです。
さらに、各店舗に電力の使用状況を「見える化」するモニターを設置しています。見えない電気をあえて可視化することで、省エネ活動の計画・実行・評価・改善を行っているとのこと。
森:太陽光パネルが屋上にあるメリットは電気料金を下げて節税するだけにとどまらず、夏の直射日光を避ける点でも、ものすごく効果があると感じます。夏の冷房費が下がり、設置にかかった費用のもとはとれました。
自然環境とともにある漬物で亀岡に貢献したい

ほかにも子どもの貧困をなくすべく支援が必要な家庭に対して「宅食」というかたちで食品を寄付したり、2つの工場において従来のボイラーから高効率ボイラーに転換をして二酸化炭素の削減を目指したり、店舗で使用しているレジ袋には植物由来成分を原料としたバイオマスプラスチック配合のものを採用したり、紙袋もFSC管理された木材再生材を使用しています。多様でサスティナブルな活動を続ける、もり。SDGsに対して今後はどのような展開を考えているのでしょう。
森:大きくは二つあります。一つは、野菜の端材を食品として再生し、利用すること。野菜って本来は廃棄する部分はないと思うんです。たとえば、かぶらならば漬物に使わない部分を冷凍し、細かくペーストして、スープの材料にしたり、みぞれ鍋の素として販売したり。これは実現したいですね。他の漬物屋さんに提案したら、実現するにはハードルが高そうだとのことだったので、だったら当社がやろうと。
もう一つは、麦芽かすの処理です。クラフトビールのブームで、麦芽かすの処理が問題になっています。麦芽かすは大量に出るうえに独特なにおいを放ち、腐敗が早いので。これを当社が引き受けて堆肥化し、畑に撒いて養分にして、そこでできた野菜で「ビールに合う漬物」をつくってみたい。それがさらに亀岡の名物になると、いいですよね。
SDGsを介して亀岡に新たな名物が誕生するかもしれません。
森:漬物で地域に貢献する、そういう動きになるよう考えているところです。漬物業界からも「もり、今度は何をしでかすんやろうな」って期待していただいているので、望みに応えたい気持ちがあります。

最後に、これからSDGsに取り組みたいと考えている企業に、アドバイスをいただきました。
森:SDGs17項目に一つも当てはまらない会社はないはず。必ず何かは採り入れていると思うんです。SDGsと自分の会社の活動と照らし合わせ、つながる部分があるのならば、そこを強化して確立し、さらにちょっとずつ増やしてゆく。あまりハードルを高く設定せず、できることからやってゆくのがいいのではないでしょうか。
京都にはいにしえの時代から、食材を無駄にせず使い切る「始末」という考え方があります。それは現代でいうSDGsにつながるスピリットです。
「SDGsを意識しはじめて4年」という森さん。しかしながら、SDGsという言葉を使わずとも始末の心を先代からしっかりと受け継いでこられています。そういう点で、昭和の頃からずっとSDGsの最先端を走る企業だったのだと、取材を通じて感じました。

参考 ※1「令和4年度食品循環資源の再生利用等実態調査結果」https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/zyunkan_sigen/r4/index.html
亀岡市SDGsアドバイザー高木超氏のコメント
株式会社もりのお取り組みをSDGsのメガネで見てみると、いくつものSDGsの達成に貢献することが分かります。例えば、漬物を製造する際に発生する生ごみを堆肥化・飼料化して廃棄物を減らしていますので、SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」の達成に貢献します。また、亀岡に自社農場を設置して、漬物の素材となる野菜を生産している行動は農業に関係するSDGsの目標2「飢餓をゼロに」にも関連します。こうした複数のSDGsの目標に貢献するだけでなく、インタビューでの「私たちの年代が後世に何を残せるのか」という森さんの言葉からは、現在と未来をつないで考える特徴を持つSDGsという概念を理解され、実際に行動に移しておられることが伝わってきます。

高木 超(たかぎ こすも)
亀岡市参与(SDGsアドバイザー)
▶ 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任助教