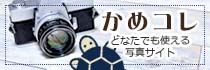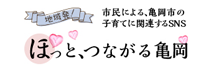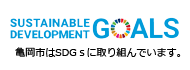本文
4歳から5歳の子どもの育ち・子育てのポイント
4歳から5歳の子どもの育ち・子育てのポイント
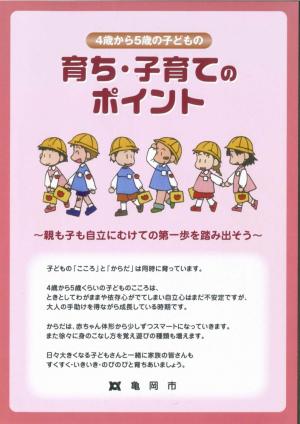
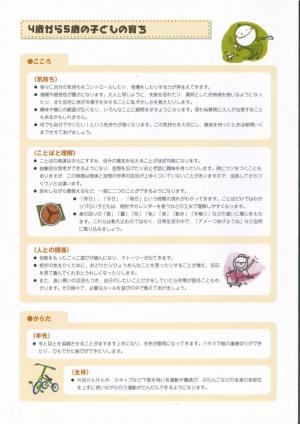
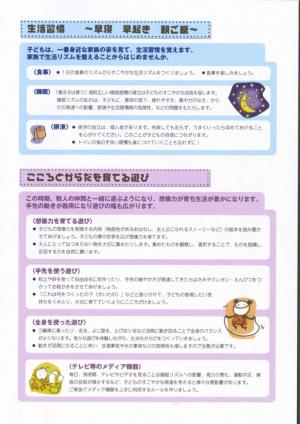

〜親も子も自立にむけての第一歩を踏み出そう〜
子どもの「こころ」と「からだ」は同時に育っています。
4歳から5歳くらいの子どものこころは、ときとしてわがままや依存心がでてしまい自立心はまだ不安定ですが、大人の手助けを得ながら成長している時期です。
からだは、赤ちゃん体形から少しずつスマートになっていきます。
また徐々に身のこなし方を覚え遊びの種類も増えます。
日々大きくなる子どもさんと一緒に家族の皆さんもすくすく・いきいき・のびのびと育ちあいましょう。
1 4歳から5歳の子どもの育ち
こころ
<気持ち>
• 徐々に自分の気持ちをコントロールしたり、我慢をしたりする力が芽生えてきます。
• 情緒や感受性が豊かになります。大人と同じょうに、失敗を恐れたり、漠然とした恐怖感を感じるようになったり、また反対に怖がる様子をみせることに恥ずかしさを覚えたりします。
• 興味や関心の範囲が広くなり、いろんなことに疑問を示すようになります。思わぬ質問に大人が当惑することもあるかもしれません。
• 何でも自分でやりたい!という気持ちが強くなります。この気持ちを大切にし、意欲を持ったときは納得いくまでさせてあげましょう。
<ことばと理解>
• ことばの発達はさらにすすみ、自分の意志を伝えることがほぼ可能になります。
• 抽象的な思考ができるようになり、空想を広げたりおとぎ話に興味を持ったりします。時にウソをつくこともありますが、この時期は現実と空想の世界の区別が上手くついていないことがありますので、成長してからつ<ウソとは違います。
• 話をしながら着替えるなど、一度に二つのことができるようになります。
• 「昨日」、「今日」、「明日」という時間の流れがわかってきます。ことばだけではわかりづらい子どもは、時計やカレンダーを使うなどの工夫で理解しやすくなります。
• 身の回りの「数」「量」「形」「色」「音」「動き」「手触り」などの違いに関心をもちます。これらは教え込むのではなく、日常生活の中で、「アメーつあげようね」など自然に取り込みましょう。
<人との関係>
• 役割をもったごっこ遊びが盛んになり、ストーリーが出てきます。
• 相手の気をひくために、おどけたりひょうきんなことを言ったりすることが増え、反応を見て喜んでくれるとうれしくなったりします。
* また、良い悪いの区別もつき、自分のしたいことだけをしていたら仲間が困ることもわかります。その時々で、必要なルールを遊びの中で教えてあげましょう。
からだ
<手先>
● 手と目とを協調させることがますます上手になり、手先が器用になってきます。ハサミで紙の連続切りができたり、ひもでかた結びができたりします。
〈全体〉
●片足けんけんや、スキップなど下肢を用いる運動や縄跳び、ぶらんこなどの全身の各部位を上手に使いながら行う運動がだんだんできるようになります。
2 生活習慣 〜早寝早起き 朝ご飯〜
子どもは、一番身近な家族の姿を見て、生活習慣を覚えます。
家族で生活リズムを整えることからはじめませんか。
<食事>
●1日の食事のリズムからすこやかな生活リズムをつくりましょう。
●食事を楽しみましょう。
<睡眠>
●「寝る子は育つ」規則正しい睡眠習慣の確立は子どものすこやかな成長を促します。 睡眠リズムの乱れは、子どもに、意欲の低下、疲れやすさ、集中力のなさ、からだの発達への影響、肥満や生活習慣病の危険性、などの問題をもたらします。
<排泄>
●排泄の自立は、個人差があります。失敗しても叱らず、うまくいったらほめてあげること を心がけてください。このことが子どもの自信につながります。
● トイレの後の手洗い習慣も身につけていくことも忘れずに!
3 こころとからだを育てる遊び
この時期、数人の仲間と一緒に遊ぶようになり、想像力が育ち生活が豊かになります。 手先の動きが器用になり遊びの幅も広がります。
<想像力を育てる遊び>
● 子どもの想像力を刺激する内容(物語性があるおはなし、主人公になれるストーリーなど)の絵本を読み聞かせてあげましょう。子どもの夢の世界を広げ想像力を育てます。
● 大人にとってはつまらない物を大切に集めたりします。集めたものを観察し、選択することで、ものを認識し 区別する力を自然に養います。
<手先を使う遊び>
● 粘土や砂を使って自由自在に形作ったり、手先の細やかさが発達してきたらはさみやクレヨン・えんぴつをつかってお絵かきをさせてあげましょう。
● 「これは何をつくったの?(かいたの)」などと語りかけて、子どもの表現したい気持ちをくみとり、大切に育てていくようにこころがけましょう。
<全身を使った遊び>
● 三輪車に乗ったり、走る、よじ登る、とびおりるなど活発に動き回ることで全身のバランスがよくなります。色々な遊びを体験しながら、丈夫なからだをつくっていきましょう。
●動きが活発になることに伴い、交通事故や水の事故などの危険性も増しますので注意が必要で す。
<テレビなどのメディア機器>
●毎日、長時間、テレビやビデオを見ることは睡眠リズムへの影響、視力の悪化、運動不足、家族の会話が減少するなど、子どものすこやかな発達を考えると様々な悪影響があります。 ご家族でメディア機器を上手に利用するルールを作りましょう。
4 ほめ方上手はしつけ上手
子どものやる気、向上心を育てるため、達成感を味わせましょう。
<聞き上手になりましょう>
● 子どもより親の方が話しをしている時間が長くはなっていませんか。
● 大きくうなずいて、「そうか、そうか」と子どもの言うことを繰り返して受け止めましょう。
●「こうしたらいいのに」と、つい答えを言ってしまいがちですが、それでは話を聞いてもらおうという気持ちがしぼんでしまいます。
<子どもは見ています>
●「明日ね」と言ったのに、次の日にはつい忘れてしまっていたり、子どもだからと約束を守らなかったりしていませんか。
● 良いことと、悪いことの区別を教えましょう。大人の事情によって、時と場合で区別が違わないように。子どもが混乱します。
私たちが生きていく上で大切なことは、 「自分が大切な人間なんだ」「生きていていいんだ」という気持ち、 「自己肯定感」を持つことです。 この気持ちは心の土台となり、この土台があってこそしつけが生きてきます。
<ほめ方上手になりましょう>
●ほめる時は、すかさず具体的にほめてあげましょう! 「〇〇ちゃんえらいね」ではなく、「〇〇ちゃん、お皿持ってきてくれてありがとう」と行動をほめてあげましょう。
● ほめることばと一緒にマイナスの指摘までしてしまうと、せっかくのほめ言葉が台無しです。 「ほらできたじゃない。でもなんで最初からそうしなかったの?」などなど。
<それでも叱ってしまうことはありますよね・・・>
●叱るときもほめるときと同じように、全人格を否定するのではなく、「〇〇するのはよくない」と行動を指摘しましょう。