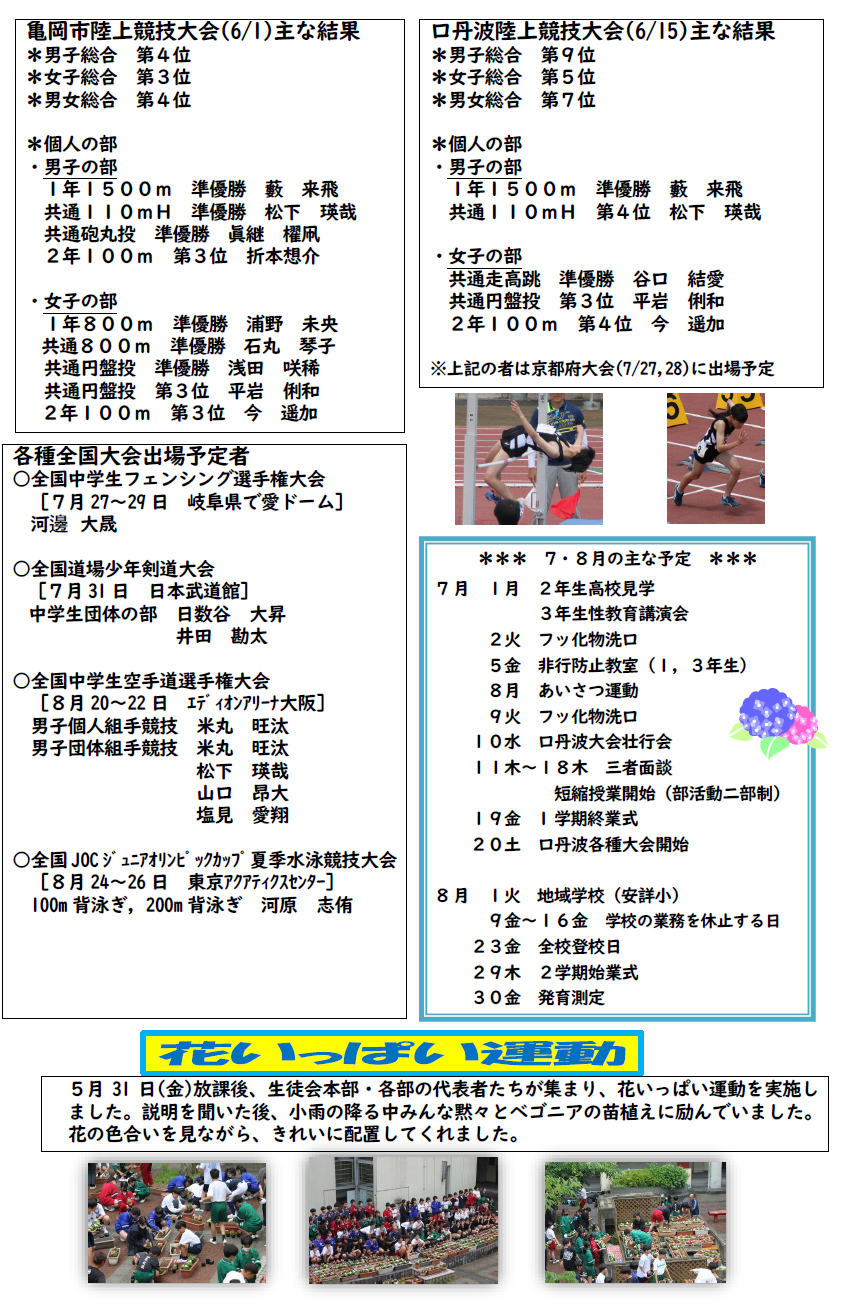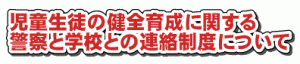本文
学校だより 7月号
「AIの進歩により、求められるものは・・・」
校庭を眺めると、「花いっぱい運動」で生徒たちが植えてくれた花々が、強い日差しに照らされて色鮮やかに、とても眩しく感じられます。例年より遅い梅雨入りの後、例年以上の猛暑が予想されますので、どうぞご自愛ください。
先日、朝の校門前で登校指導をしていると生徒から「校長先生、お手紙です。」と元気よくお手紙を渡してもらいました。その手紙は、昨年度同様剣道の全国大会出場決定のお知らせでした。ちょうど一年前は、そのことを朝学活で伝えていただいたところ、朝学活終了後には、三競技5名の全国大会出場を知ることとなり、喜んだことを思い出しました。今年度は、修学旅行の前後に、フェンシング大会で河邊大晟君、剣道大会で日数谷大昇君、井田勘太君、空手大会で米丸旺汰君、松下瑛哉君、山口昴大君、塩見愛翔君、水泳大会で河原志侑君の四競技8名の全国大会出場が決定しました。おめでとうございます。そして、全国大会での活躍を、詳徳中学校のみんなで応援したいと思います。頑張ってください。
さて先日、次のような新聞のコラムが掲載されていました。
「AIは仕事をどう変えるか」という見出しで「AIの進歩は、仕事にどのような影響を与え、個人にとってはどのようなスキル(技術・技能)の上昇が求められるか」というものでした。「タクシー乗務員の仕事は、運転・接客・需要予測(お客さんがどの時間帯どの地域にいるか予測すること)などいくつかのタスク(作業)で構成されている。AIが自動運転をし、需要予測を代替するとすれば、タクシー乗務員に重要になるのは接客のスキルかもしれない。また、AIが契約書をチェックし、画像診断をするのであれば、弁護士や医師も同様かもしれない。」とのことでした。つまり、高い専門性はAIに任せ、高い人間性が求められるという指摘だったのです。
「なるほどなぁ」と思いながら、2年生のホールを歩いていると、掲示板に多くの壁新聞が貼られていました。それは、2年生社会科の地理分野の発表で「日本は災害の多い国であるにもかかわらず、人口が多いのはなぜだろうか。」という表題が記されていました。そして、各学級各班からの主張のレポートが掲示されていました。
一つを紹介すると次のようなものでした。「日本の人口が多いのは川が多いから。」その理由として(1)地震が多い国は人口も多い。(2)地震が発生すると山ができる。(3)山ができると川ができる。(4)川があると人が集まる。(5)川があると貿易が栄える。結論として「災害の中にも人間が暮らしていく上でメリットがある。」「人間が暮らしていく上で水は必要な資源であるため川の周りに人は集まることが分かりました。」その他にも「災害対策が進んでいるから」「日本は災害の多い国である。でもその分、他国から高い評価を受けるくらいの多くのメリットがある国でもあるから」など、グラフや写真、イラストなどを交えて、多くの主張が示されていました。
一昨年度から、本校では「正解のない問い」に最適解を考えさせる「課題解決型の学習」に取り組んでいます。現代の日本には、少子高齢化やグローバル化への対応、労働人口の減少による国家財源の減少、社会保障問題など、これまでの思考法やAIでも導き出せない問題が山積しています。その時代において「考える能力」「課題解決力」が必要とされているからです。このような力を身につけるためには、様々な課題に対するアプローチ方法や解決方法を自ら想定し、仮説を立て、検証し、言語化して発表できる能力が必要です。
また、今回の社会科のレポートの裏側には、各班での話し合いがあります。話し合いでは、「無知・無能だと思われる不安」や「邪魔をしている・ネガティブだと思われる不安」を取り除き、「発言の機会を平等にする」「人の話を肯定的に聞く」「協力的な話を行う」ことなどを大切にした、心理的安全性が確保された中での話し合いが重要です。AIが発達してきた社会に求められる、人間性を高めるための授業が行われていることを実感するとともに、そのような授業作りに取り組んでくださっている先生方に、感謝の気持ちでいっぱいです。
6月26日には、午後から課題解決型学習に向けての 研究会を行いました。このような研究授業が行えるのも、 地域や保護者の方々のご理解とご協力のおかげだと思います。 併せて、子供たちの心理的安全性を確保しつつ、自由な発想を 大切にし、人と協力する態度の育成に向けて、日々の学校教育 活動を行って参ろうと思います。今後とも、本校の教育活動に ご理解とご協力の程を、今まで同様よろしくお願いいたします。
校長 川口 研一